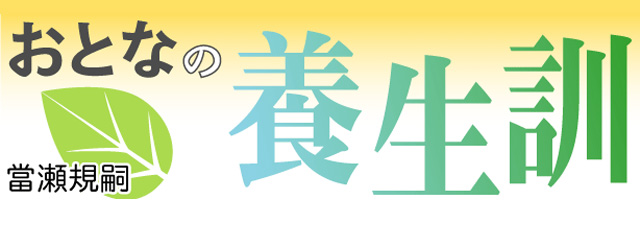口から肛門までは一本の管でつながっていて、それを消化管と総称します。胃も腸も消化管に含まれます。消化管では、食べ物が中から管の壁を押し広げると、運動がさかんになり、食べ物をどんどん肛門の方向へ運ぶという反応がおきます。これを「腸の法則」というのです。これにより口から入った食べ物は、自然と肛門に向かって運ばれて、途中で消化吸収が行われます。ところが、この腸の法則に従わない部分が1カ所だけあり、それが胃なのです。
胃に食べ物が入って押し広げられても、胃は運動を起さず、胃の壁がさらに伸びて、食べ物を胃の中に受け入れようとします。これを受容弛緩(じゅようしかん)と呼びます。もちろん、しばらくすると今度は胃の運動が活発になり、食べ物は腸へ送られます。
これは、食べ物を一時的に胃に貯えて、その間に胃液による消化をすすめ、腸に負担をかけないように少しずつ食べ物を送り出すという、胃の役割を果たすためのしくみなのです。胃の受容弛緩のお陰で、一度にたくさん食べても、胃に貯めておくことが出来るので、私たちは1日3食で済んでいるわけです。
ところで、胃の受容弛緩は、鍛えることが出来ます。通常はある程度の量を食べると受容弛緩が限界になって、お腹が一杯になるのですが、毎食ごとにお腹いっぱいの食事を食べ続けると、次第に受容弛緩が強くなってくるのです。ですから知らず知らずのうちに、お腹一杯となる食事の量は増えていき、食べ過ぎ、大食いの習慣が根付いてしまうのです。
テレビで活躍するフードファイターたちは、胃が恐ろしいぐらいに大きくなることが分かっています。詰め込むとみぞおちから下腹部まで全体に胃が拡がるのだそうです。もちろん、元々、そういう素因があったのだと思いますが、彼らはやはり、胃を大きくするトレーニング、つまり受容弛緩の強化に日々励んでいるそうです。
フードファイターでない私たちは、そうは行きません。毎日満腹になるまで食べ続けると、本当に肥満になって、メタボリック症候群になって、糖尿病になって…。やはり、先人の教えを守り、腹8分目に心がけるべきです。そうすれば、いずれ受容弛緩も元の強さに戻りますから、より少ない量で満足が得られるようになりますよ。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)