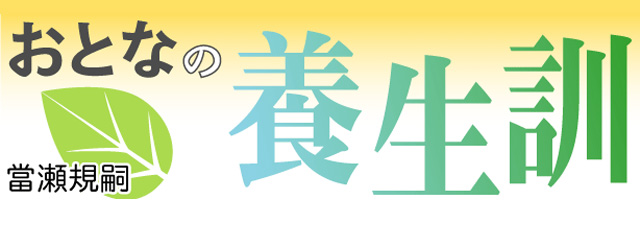忘年会の宴会となれば、コース料理が定番ですね。コースには、かなり高い確率で刺身の盛り合わせがでます。和食の宴会に刺身はつきものです。さらに最近は、和食だけでなくイタリアン料理のカルパッチョも一般的になったので、刺身を食べる可能性はますます高まっています。
冷凍、冷蔵の輸送技術も開発されて、極めて新鮮な状態で港から料理店まで運ばれるので、昔は「刺身は不可能」と思われていた、サンマやサバ、サケも刺身で出てきたりします。すごい世の中になったものです。
でも、新鮮な魚の刺身が必ずしも安全とは言えません。雑菌が繁殖して食中毒を起す危険性は限りなく低下しましたが、逆に魚に付いている寄生虫も死なないことになるので、寄生虫の害が発生する危険性は、むしろ高まっています。
有名どころで言うと、アニサキスです。イカ、アジ、サバ、サケ、ホッケなどの魚の内臓と内臓回りの身に、実は、必ずと言っていいほど潜んでいます。人に寄生することはないのですが、生きたまま食べると、胃酸に苦しんだアニサキスが、逃れようと胃壁に刺さり込むので、猛烈な激痛が襲います。
こうなると、内視鏡でアニサキスを胃の壁からつまみ取るしかありません。食べてから数時間以内に発症するので、大抵は救急車のお世話になることになります。
昔の人は、刺身に寄生虫がいることはよく知っていたので、いろいろな防御策を打っていました。イカは細く切ってイカそうめんにします。こうして虫を切り殺そうというわけです。だから、幅広のイカの刺身は要注意です。
アジもそのままの刺身にしないで、タタキにします。こうなれば、虫はひとたまりもないでしょう。虫は冷凍で死ぬので、身を一旦凍らせてから刺身にするサケのルイベも、こうした知恵の一つです。
酢でしめるのも、虫を殺す方法です。昔のしめ鯖は、身が白くなるほど長く徹底的にしめていたので、虫は完全死滅でした。しかし、最近のグルメブームのせいで、しめ鯖は身の色がかわらない刺身のようなしめ鯖が主流になっています。もちろんおいしいのですが、これは結構危険です。この程度の軽い酢では、虫が死なない可能性が高いからです。そうめん、たたき、ルイベ、強い酢しめ、が養生訓です。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)