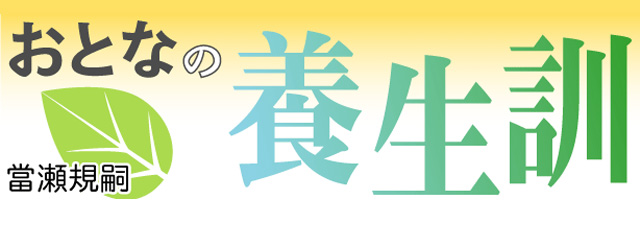普段通りの仕事をこなしているのに、しきりと汗を拭いているビジネスマンをよく見かけます。いわゆる「汗っかき」と呼ばれる人です。もちろん生まれながらの体質として、汗をかきやすい人もいますが、それ以外にも原因があります。
一番に考えられるのは、肥満との関係です。脂肪が皮膚の下に貯まることに原因があります。元来、皮膚はとても重要なはたらきを持っています。一つは、外の環境から体内を仕切ることで、体内の環境を保全することです。皮膚がしっかりしていれば、外から病原体が侵入しません。
もう一つとても大事な役割は、体温を調節することです。人は生きていることにより、細胞から熱を発生させます。実は食べた食物のエネルギーの80%は熱を生じるのに使われているのです。この熱が体に貯まるだけだと、体温はたちどころに上昇し、体内のタンパク質はすべて壊れて死んでしまいます。つまり「ゆであがって」しまうのです。
そこで、体温を一定に保つために、生じる熱を出さなければなりません。皮膚は外の環境と接しています。なので、体に生じた熱を出すのに一番都合のいい場所ということになります。
考えてみれば、気温が通常の体温(36度ぐらい)より高くなることは、めったにないわけですから、皮膚は空気によって常に冷やされているということになります。ですから、体内の熱を皮膚に伝えれば、空気で冷やされて、自然と熱が抜けるはずなのです。
太っている人では、体内の熱が皮膚に伝わる前に皮下脂肪が立ちはだかります。脂肪は熱を伝えにくい性質を持っているので、熱は皮膚まで伝わりにくくなり、体に貯まりやすくなっているのです。秋の動物が丸々と太るのは、皮下脂肪で熱を体に貯めて、冬の寒さを乗り切ろうとしているからです。
さて、皮下脂肪のために熱が出にくくなると、体温が上がって危険なことになるかもしれません。そこで体温を一定に保つために、発汗が始まります。汗は皮膚の表面で蒸発することで皮膚から熱を奪うことができるので、発汗すると皮膚は急速に冷えるのです。
こうして体内の熱は外に出たことになります。つまり、皮下脂肪が熱を出しにくくしているので、帳尻を合わせるために余計に汗を出しているという訳です。発汗は体に負担をかけます。やはり、減量に努めましょう。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)