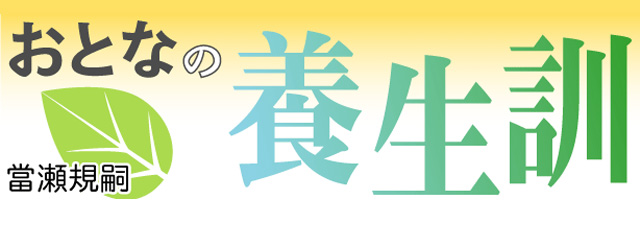朝、なかなか目が覚めず、危うく遅刻、という経験を持つ方は、たくさんおられると思います。たびたびそういう目に遭うので、「朝は苦手」と思っている方もおられるでしょう。一方、朝は早起きして、会社にも余裕で出社。朝が一番快調だと、早々に仕事に取り掛かる人もいます。こういう差は、どこから来るのでしょうか?
もちろん、前夜に飲み会などあって、夜更かししたのなら、朝起きられないのは納得です。しかし、前夜、家で過ごしているのに、次の朝起きられない人も多いようです。こうした方は、昼夜一日の変化に対応している体内時計と呼ばれるしくみに狂いが生じている可能性があります。
体内時計が狂うと、夜、12時を過ぎても眠気が差さず、つい夜更かしになり、逆に朝は、眠りからさめにくくなるという症状になります。おそらく、残業やお付き合いなどが延々と続くうちに、体内時計が狂うのでしょう。
さて、その対処法ですが、早く起きようと思って、早めに床についても、眠気が差さなければ、床の中で悶々とするだけ。眠れないことが気になって、却って目がさえてしまったりします。対処のポイントは朝にあります。
体内時計は、全く独自に動いているのかというと、そうではありません。日の光を浴びることで、体内時計は調節される仕組みがあります。だから、地球の裏側に行って、初めは時差ボケでひどい目に会っても、1週間もすれば、現地の朝晩のリズムに合うようになるのです。
特に大事なのは、人は眠っている間も周りの光の量を目で常に感じ取っていることです。試しに、まぶたを閉じて天井に顔を向けてみてください。何となく明るさを感じて照明がついていることを確認できるはずです。ですから、朝、起きるべき時間に朝日を浴びながら起きるようにするのが効果的なのです。
体内時計が狂っていると思われる方は、寝室に問題があります。たとえば、窓のない部屋だったり、窓に厚めの遮光カーテンをしていたりする場合です。これでは、朝の光を浴びることができないので、生体時計が調整されず、目が覚めないということになりがちなのです。
ですから、寝室は東側に窓がある部屋にすべきで、カーテンは薄目がお勧めです。そうすれば、夜が明けると自然と部屋の中に朝の光が満ちて、自然と目が覚めていくようになります。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)