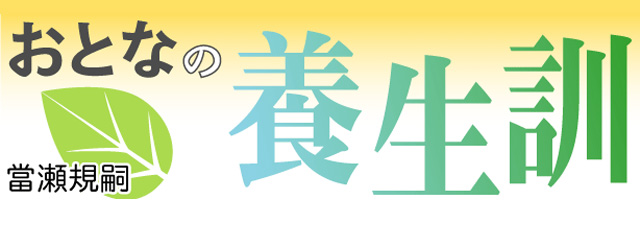便通を健康のバロメーターと考えている人が大多数を占めると思います。実際、病院でも便通の状況を患者さんから伺うのは、診察のイロハのイとなっています。そこで便通はどのような仕組みで決まっているのか考えてみましょう。
食べ物を食べてから、消化管を通って消化吸収がすすみ、24時間から72時間程度で、便として排泄されるのが通常とされます。1回に排出される量は食べる量と内容、消化吸収の度合いによって大きく異なり、一定の量とは限りません。
ですから、回数の方が目安として使いやすくなります。一般には1日1回の排便が標準的と考えられています。では、2日に1回は異常かというと、そんなことはありません。2日1回でも、3日1回でも、定期的に便通があって、おなかの調子自体が変わらないのであれば、問題はありません。
ただ、あまり便通の間隔が長くなると、大腸に溜まっている便の水分が吸収されて、徐々に固くなり、排便しにくくなる危険性があり、これは便秘につながります。
では、便秘の判定はというと、排便が3日以上ない、あるいは、毎日排便があっても残便感があるという場合、便秘を疑うことになりますが、診察の結果、もっと長い間隔の人でも問題がないこともままあります。しかし、やはり用心に越したことはありません。
食べたものが次の日に全部出るというのが理想的と思われていますので、便通を改善する方策も考えてみます。肛門の前にある直腸は通常空っぽです。そこに便が進入すると、これが脳に伝えられ便意を催し、排便することになるのです。
ですから、便の進入を促進する手立てが重要です。それに最適なのは胃大腸反射と呼ばれる反射です。人は、空っぽの胃に食べ物などが入り、胃が膨らむと、それを合図に大腸の運動が活発になるという反射が起こります。
次の食べ物が来たので、大腸の中を空ける必要があるからです。この結果、大腸の終わり部分に溜まっている便は、押し出されて直腸内に進入するわけです。
空っぽの胃に食べ物が入る一番の機会は、朝食時です。睡眠中は全く食べ物を口にしないからです。したがって、朝食の後に便意を催す人が多くなるのです。規則正しい排便には、十分な睡眠と毎朝の朝食が一番だといえます。便通が気になる方、まずは睡眠を見直しましょう。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)