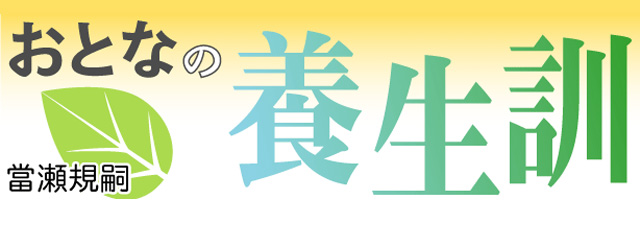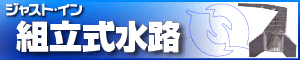人の感覚の中で、においは視覚や聴覚などの他の感覚と比べて、特別な感覚です。一つは、とても慣れやすい感覚であるということです。同じにおいを感じ続けると、次第に感じられなくなっていくのです。ですから、人は自分のにおいを感じることはほとんどありません。
においの感覚は、元来、動物が環境の変化を知って、危険なものから身を守ったり、食べ物のありかを探り当てたりするために使われています。だから、身の回りにあるもののにおいには慣れておいて、新たなにおいの出現に気が付きやすくしているのです。
においは身の回りの変化を知るための感覚なので、睡眠中も働いています。たとえば、味噌汁やコーヒーのにおいで朝目が覚めたという経験を持っている人も多いと思います。睡眠中は、他の感覚は基本的に働いていないので、目は見えませんし、音は聞こえません。
においの感覚が眠りにくいのは、においの感覚情報が脳に直接入力されているからと、説明されています。その入力されている領域は、記憶が形成される領域の隣りといわれています。なので、においと記憶は密接な関係があります。動物では、においによって、自分の仲間なのか、敵なのかを判定しています。これはにおいが記憶のかかわりを示しています。
人の場合、あるにおいをかぐと、昔の記憶を思い出すというようなことが、よくあります。だから、懐かしいにおいというのが存在します。たとえば、学校のにおいを感じると、昔の学校の様子が頭に浮かんできて懐かしくなったりするわけです。草のにおいや、潮の香りをかぐと故郷を思い出すという話もよく聞きますね。
このにおいと記憶の関係を逆手に取って、物事を記憶するときに特徴あるにおいをかいでおくと、そのにおいを再びかぐことで、物事を思い出しやすくなることが分かっています。また、ハーブなどの香りは、記憶力が高まって、勉強がはかどるという説も存在します。
私もウイスキーの利き酒をやっていると、初めて飲んだはずの銘柄なのに、懐かしさがこみあげてくるということがよくあります。「ああ、あの時のお酒だ、あの時は、こんなことがあったな…」なんて感じです。
バーで香りの高いカクテルやウイスキーをやりながら物思いに沈んでいる人って、結構いるのですが、格好つけているのじゃなくて、本当に懐かしい何かを思い出しているんでしょうね。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)