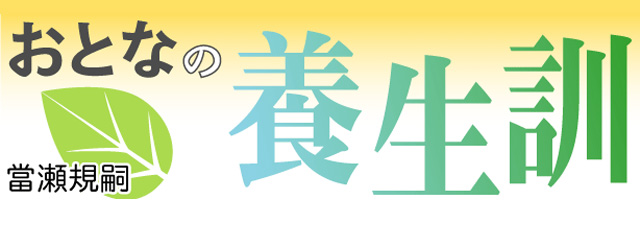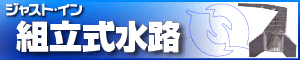基本的に食べ物は腐敗します。腐敗を抑えることで、食べ物を貯蔵することが可能になり、必要なときに食べたり利用したりすることができるようになります。食べ物を貯蔵する方法で、簡単で効果的なのが塩蔵です。いわゆる塩漬けです。塩をすり込んだり、塩水に漬け込んだりすると、食べ物の腐敗は起こらなくなります。なので、洋の東西を問わず、さまざまな食べ物が塩蔵されています。
なぜ、塩で腐敗が抑えられるのかというと、塩が腐敗を引き起こす細菌やカビの増殖を抑えるからです。といっても、塩が菌を殺す作用を持っているのかというと、そうではありません。もしそうなら、巨大な塩水の塊である海に生き物はすめないことになります。
また、塩は塩粒のままでは、腐敗を抑える効果がほとんどなく、塩が水に溶けた状態、つまり塩水になっていなければなりません。それも濃い塩水でなければならないのです。
腐敗を引き起こす細菌やカビは細胞でできています。細胞の中には主にカリウムを含む塩水が存在し、この塩水の中でさまざまな生物としての反応が起きて、生存、増殖をすることになります。もし、細胞の周りに濃い塩水があったとすると、細胞の中の水は、濃い塩水の方に移動します。これは浸透と呼ばれる物理的な現象で、これによって細胞の中の水が減少します。つまり脱水が起こるわけです。そうすると細胞はつぶれてしまい、死滅することになります。
ですから、濃い塩水に食べ物をつけると、細菌やカビの細胞はつぶれ、増えることができなくなり、食べ物の成分が細菌によって分解されることが起こらなくなるのです。つまり腐敗が起こらないのです。
一方、細胞の中の水と同じ濃度の塩水では、浸透が起こらないので、細胞が壊れることはありません。したがって、腐敗を防止するには、塩水の濃度が大事で、薄い塩水では役に立たないのです。
というわけで、塩蔵した食べ物にはたくさんの塩が含まれています。魚の干物や塩辛、イクラ、カズノコ、からすみ、どれも塩辛いものです。おせちなど保存が前提の料理では味付けが濃くなるのも同じ原理に基づきます。塩蔵品は珍味が多く、おいしいものですが、食べ過ぎると塩分を大量に取ることになるので、血圧が気になる人には注意が必要です。塩分は控えめに。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)