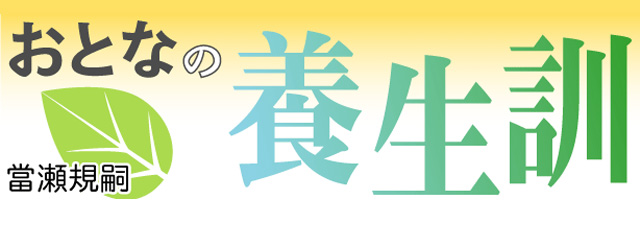年末から年始にかけて、忘年会、クリスマス、お正月、新年会と、お酒や食事をたくさん取る機会が続きました。こうなると、胃腸も連日の酷使で、疲れが出てくるといわれます。そこで、正月の7日には七草がゆを食べて、胃腸をいたわるという風習が定着しています。七草は消化を整える効用があるとされ、ビタミンも多いので、年末年始のごちそう続きで疲れた胃腸の働きを整えるというわけです。
しかし、疲れるのは胃腸だけではありません。とりわけ、毎日のようにお酒を飲んだ方には、肝臓の疲れにも気を付けるべきでしょう。
肝臓は吸収した栄養の貯蔵と体内への再分配を行い、また、摂取したアルコールの分解処理といった解毒作用をする大変重要な臓器です。なので、暴飲暴食が続くと、肝臓に相当な負担がかかり、肝臓を傷めてしまう危険性があります。
しかし、肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、少々のトラブルが肝臓に生じても痛みなどは感じなく、トラブルを自覚しにくい臓器なのです。ただ、肝臓の働きが弱まると、倦怠感や眠気、食欲不振などが出やすくなることも指摘されています。
疲労に関係するとされている疲労物質は、肝臓で処理されると推定されているので、肝臓が弱ると疲労物質がたまりやすくなるためと考えられます。また、脂肪の消化吸収に肝臓が重要な役割をしていることから、肝臓が弱ると、脂っこいものが食べられなくなることも分かっています。
つまり、年末年始に続いたお酒とごちそうの処理のため、肝臓を酷使することになり、負担がかかって、なんとなく疲れを感じたり、食欲が落ちたりする危険性が高くなるのです。これが、まさに飲み疲れといえる状態なのです。思い当たる方は少なくないと思います。
飲み疲れ対策としては、まず、お酒を控える、できればしばらく断酒することです。また、十分な睡眠により、体全体の疲労を取るのも重要です。さらに、肝臓の働きを回復させるために、肝臓の重要なエネルギー源であるアミノ酸を多く含んだ食品を積極的に取ることです。
それは、カキ、シジミ、アサリなどの二枚貝を食べることです。特にカキにはアミノ酸の一種であるタウリンやオルニチンが豊富だとされます。さらにタウリンが豊富なイカやタコもお勧めです。仕事始め以降、なんとなく力が入らないと感じたあなた、試してみてはいかがでしょう。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)