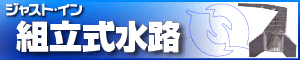中村拓哉社長
導入アイデア相談から
経済界のさまざまな分野で人工知能(AI)という言葉が聞かれるようになって久しい。北大発ベンチャーの調和技研(本社・札幌)は国内でも有数のAI開発企業だ。業界の現状や建設業との接点、今後の展望について中村拓哉社長に聞いた。
―多くの人がAIでの課題解決を考える時代になった。受注が増える一方では。
5年前までは一般企業に技術をイメージしてもらうだけでも一苦労だったが、最近は説明がいらなくなった。今は特段営業をかけなくても電話や電子メールで相談が来る。社外取締役の鈴木恵二はこだて未来大教授や川村秀憲北大教授経由で案件が入ることも多い。これまでの取引企業数は延べ50社になる。社員数は役員や顧問を入れて今約50人。売上高はこのところ毎年倍増のペースで、2021年3月期は約5億円を見込んでいる。
―設立は11年前。中村社長が創業したのか。
そう思われがちだが私は創業者ではなく、エンジニアでもない。私自身は商学部を出て拓銀に入り、その後日立グループのソフトウエア会社で働いていた。ここで北大と接点ができ、AIの大学院調和系工学研究室から生まれた調和技研の運営を手伝うようになった。
当初、取締役は社長を含めて全員学生で、顧問に大学教員という体制だった。事業の成長性を感じた私が日立グループを辞め、3代目社長に就いたのが今から7年前。むろん苦労ばかりで、多くの関係者から少しずつ仕事を頂いてしのぐ中、世間でAIが広まり道が開けた。
―国立大学との結び付きが強い分、一般のIT企業より低価格を出せるのでは。
低価格路線はまったく目指していない。むしろ、仕事の品質に見合う利益をいかに確保してエンジニアの給料を上げられるかが経営課題だ。というのも優秀な人に高給を出せなければ人材流出が待っている。この業界では国をまたぐ転職も当たり前。受注も人材も世界との競争だ。
―AI導入に関心を持つ企業はまず何をすればいいか。
原則的にアイデアさえ相談してもらえれば専門知識は必要ない。業務に実際どのように導入するか、当社の専門家が具体策を検討する。そのためには業務内容を現場レベルで把握する必要があり、開発前に2、3カ月のコンサルティング期間があると考えてほしい。
高度人材を張り付けるため、この段階の費用は数百万円が目安。開発に入ると、当社がAIの脳部分に当たるエンジンを作り、それを既存の業務システムに組み込む作業は各社の出入りのシステム会社にお任せする。開発費用は内容次第で大きく変わってくる。
―建設業のAI導入状況は。
当社はまだ建設会社との取引はない。今は設計や修繕といった関連企業からの相談が、各社出入りのシステム会社を通じて当社に来ている。例えばコンクリートの点検用の画像解析、基礎的な建築設計などだ。ただ、当社に限らず全体的に建設業界へのAI導入はまだ例が少ない。もっと役に立てると考えているため、ぜひ相談いただきたい。
―昨年末バングラデシュに現地法人を設けた。
首都ダッカで4人雇用し、春にはさらに増員する。日本のAIブームは3年後には落ち着くだろう。今後、開発場所としても受注先としても外国の重要性は高まる。昨年は市場調査でベトナム、タイ、ロシアにも足を運んだ。環境変化を読み、先手を打ちたい。
(聞き手・吉村慎司)
中村拓哉(なかむら・たくや)1961年6月札幌市生まれ。86年慶応大商学部卒、北海道拓殖銀行入行。日立ソフト勤務を経て2011年に調和技研取締役、13年から現職。