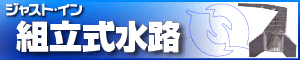水環境の変化が地球温暖化や大気環境を知る手がかりに
摩周湖の近隣5町と国、道、研究機関で構成する摩周湖環境保全連絡協議会は8月25、26の両日、湖水モニタリング調査をした。透明度の高さや神秘性を守るため、クラウドファンディング(CF)で協力金を募るなど、行政の垣根を越えた取り組み。調査に同行した。(釧路支社 三浦郁実記者)

透明度などを測定した
阿寒摩周国立公園内にある摩周湖は最大水深約212mのカルデラ湖で、1931年には世界一の透明度41・6mを記録。81年から国立環境研究所が調査を続け、94年には国連環境計画のGEMS/Water(全球陸水水質データ監視計画)における観測地点として日本の湖沼で唯一登録された。
2018年度で国の調査が終了したことを受け、弟子屈町、標茶町など近隣5町と環境省、国立環境研究所、北海道立総合研究機構などの関係機関で同協議会を設立。19年度からはCFで協力金を集めて継続している。
調査地までは徒歩で30―40分かかる。平地を歩くのではなく、急斜面を沢づたいに下りる。足下ばかり注視していると予期せぬ倒木が行く手を阻む。狭いところでは道幅が片足分ほどしかないルートもあった。転びつつ、背丈ほどあるささをかき分けて進むと青く輝く湖面が広がる。霧の摩周湖と呼ばれるが、この日は晴天に恵まれ、風も落ち着いていた。湖面が鏡のように風景をそのまま映し返していた。
最大水深で計測するため、湖心部の観測点までボートで移動。ロープでつないだ水質測定器をボートからゆっくりと湖底まで下ろし、表層から湖底までの水温、溶存酸素量、クロロフィル、濁度などを計測した。水質調査で使用する機器はしっかり沈むことが大前提のため、基本的に重たい。下ろすのも引き上げるのも根気が必要だ。
透明度は透明度板というロープにつながった直径30cmの白色円盤を用い、ボートから肉眼で円盤を確認できる深さまで下ろして計る。肉眼での計測のため天候などに左右されやすいが、当日は好条件に恵まれ、透明度は21・1mだった。
河川の流入出がなく隔離された環境にある摩周湖は、主に大気から影響を受け続ける。水質を調べることで地球温暖化や大気環境を知る手がかりとなる。
全ての調査が終わり、再び林道に入る。急斜面のため蛇行したルートを進み、スイッチバックする電車になった気持ちで斜面を登るがなかなかゴールが見えない。笹にしがみつきながら何とか登り切った。
1日のみの同行だったが、調査やその大変さは体感できた。水環境は目に見えないため、調査の重要性が理解されにくい部分もある。しかし、調査をすることで、見えない部分を視覚化できる。環境変化のプロセスを捉えるためにも調査が継続されることが望ましいと感じた。
(北海道建設新聞2020年9月1日付11面より)