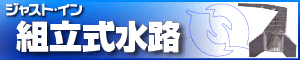北海道胆振東部地震が発生して6日で丸2年がたつ。厚真町では、10月にも災害公営住宅が完成し、仮設住宅に住む町民の移転が始まる。復旧が進む一方で、宮坂尚市朗町長が「震災を伝える役割がある」と話すように、震災の記憶を風化させず語り継いでいくことも重要となる。最大震度7を観測した災害発生時の厚真町に関わった人たちにあらためて当時の状況、思いなどを聞いた。
地域業者なくては災害時対応できず
菱中建設(本社・札幌)の山崎啓二社長(当時専務)が駆け付けた道道上幌内早来停線は車が通れるような状態ではなく、すぐに啓開作業に当たった。「何をやったらいいか、どこに行ったらいいか分からなかった」。重機で一斉に作業することは難しく、土砂を取り除いては進み、また取り除いては進んでいった。
山崎社長は日頃の災害訓練の成果が生かされているとしたものの、「復旧をよりスムーズにするためには、役所も業者も含めた指示命令系統の一本化が重要」と指摘。そして「地域に建設業者がいないと災害時の対応ができない」と言い切る。
土砂で流された家衝撃で言葉もなく

地震直後の厚真川河道の土砂撤去の様子。
二次災害を防ぐため作業は一刻を争った(小金澤組提供)
小金澤組(本社・苫小牧)は当時、室蘭建管発注の厚真川改修を丸彦渡辺建設(同・札幌)と共同体で担当。所長の池渕貴司さんは午前4時半ごろ現場に到着した。
池渕さんは14年ほど厚真川の改修に携わっている技術者。「工事でお世話になった人たちの家が土砂で押し流された。衝撃的で言葉がなかった」
現場で使用していた重機が無事だったため、厚真川の二次災害防止に向け閉そく除去作業に取り掛かった。最終的に集まった重機は72台。疲労や度重なる大きな余震で皆、疲弊していた。
安全管理などでサポートした小金澤組の椎名心専務(当時常務)は「地場に建設業がいないと、災害が起こったとき大変なことになる。こうしたことを少しでも周りの人に理解してほしい」と訴える。
池渕さんは「農家の人の作付面積が昨年よりことしの方が多くなったり、厚真特産のハスカップを植えたりしているのを見るとうれしい」と、目に見えつつある復興に思いを寄せる。
災害FMで厚真の情報発信し続ける
被災した町民に生活情報を伝えたのは、役場職員や地域おこし協力隊が中心になって設立した災害エフエムラジオだ。北海道総合通信局から放送用機材を借り、9月20日に臨時災害放送局「あつま災害エフエム」を開設。1日3回の放送で給水情報や風呂、避難所の情報などを発信し続けた。
設立当初から関わった役場の丸山泰弘建設課主査は「ラジオだと車で聞けたり、聞きながら別のことができたりする。あらためてラジオの良さが分かった。ただ、もっと早く放送を開始できたら災害発生初期の情報を流すことができたし、決まった時間ではなく、ずっと情報を流すことができれば良かった」と振り返る。
災害エフエムは災害復旧に一定のめどが立つ年内には放送を終了する。
地震きっかけに建設会社へ就職

巨大地震を経験し、〝復興を担う建設業の道に〟と将来の進路を決めた金谷さん
被災当時、岩見沢農高2年生だった金谷柊?さんは、地震がきっかけでその後の将来が変わった若者だ。実家は町内で畑作農家を営んでいる。
金谷さんは地震後すぐ厚真に帰省した。実家は納屋が倒壊する被害に見舞われたが、まち全域にはもっと悲惨な光景が広がっていた。
高校の授業でも「災害の復旧・復興を担っているのは建設業」と学び、〝災害=警察や自衛隊〟という意識が改まった。地震以前には別の職種への就職を希望していたが「災害復興に携わる建設業界に入りたい」との考えに変わり、この春、砂子組(本社・奈井江)に就職した。
「まだ2年なんだ…」。高校を卒業し社会人になった。しかし、金谷さんの目には地震が発生してから過ぎた時間と自分の成長の度合いが比例していないように感じる。帰省するとまちはきれいになっているが、かつて見た風景は残っていない。「自然災害の対応は難しいと思う。地域にとって何が良いのか、地域から頼られ、信頼されるにはどうしたらいいのか」。若者の模索は今後も続いていく。
(北海道建設新聞2020年9月4日付11面より)