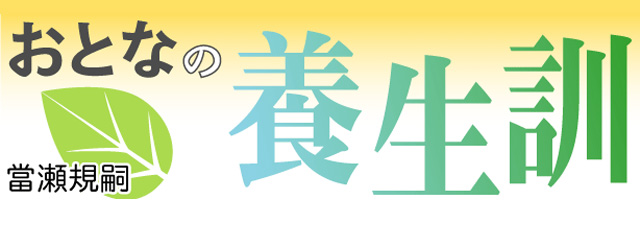昔からの健康法として「頭寒足熱」があります。足はとかく冷えがちなので、温める、頭は熱くなりやすいので冷やした方がいい、ということです。とりわけ冬には効果的と思われています。冬はとかく手足が冷えがちで、冷え性も悪化します。一方、暖房の効いた室内では熱が上にあがりやすく、頭のあたりが熱くなって、のぼせることもあるのです。そこで、こたつや床暖で足を温め、頭は風通し良くして、部屋の上や天井に熱がたまらないように心掛けるのがいいのです。
実は、かぜをひいたときの対処法にも通じるものがあります。かぜをひいて熱が出ると、おでこに冷やしたぬれタオルを当てたりします。実際は、ぬれタオルだけで熱はひかないのですが、熱でぼーっとした頭には、ひんやりとした感覚で楽になるのです。
一方、熱が上がるときには、手足が急に冷たくなり、悪寒を感じるものです。そこで、手足を温めることもよくあります。欧米では、かぜをひくと、頭を冷やすと同時に、足をお湯につける対策が伝統的にとられます。これはまさに頭寒足熱であります。つらいかぜの症状を和らげる効果があります。ただ、これだけでかぜが治らないことは、医学的に証明済みです。
そもそも頭は熱がたまりやすい部位です。それは、脳が大量のエネルギーと酸素を消費する臓器であり、それを賄うために、大量の血液が常に流れ込んでくるからです。血液は体の熱を運ぶ効果があるので、血流が多い部位は温度が上がり、血流の少ないところは温度が下がります。というわけで、血流の多い頭は熱がたまりやすくなっているのです。
これを放置すると、高い温度のために脳の働きが鈍ってきて、いわゆる「のぼせ」の状態となります。したがって、頭を冷やすことが必要となります。要は頭の周りを風通し良くして、涼しくすればいいので、「頭寒」は言いすぎですね。「頭涼」でいいのではないかと思います。
足が冷えやすいのは、心臓から一番遠くに位置するからです。特に気温が下がってくると、血液の熱が奪われ体温が下がることを防ぐため、足の血管が締まって血流が減ります。こうして、足はさらに温度が下がり、冷えを感じることになります。足は熱するのではなく、温めるのがいいわけで、「足温」が適切です。
「頭寒足熱」ならず「頭涼足温」で、冬の寒さを乗り切りましょう。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)