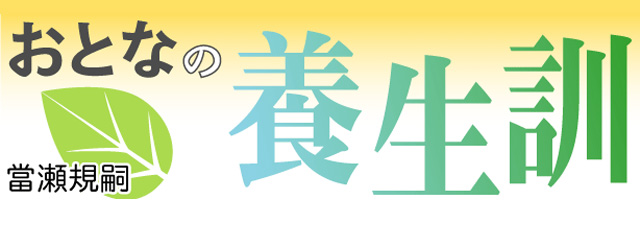感染とは、病原体が体に侵入して増殖したことを指します。病原体が体の表面に付着しただけでは感染ではありません。感染といえる病原体の増殖の仕方は、病原体の種類によって異なります。
細菌は自ら細胞分裂を繰り返して増殖するので、体の中で水分や栄養などの環境が整えば、増殖して感染が成立します。一方、ウイルスは自らの力で増えることはできません。必ず、取り付いた生物の細胞の中に侵入して、その細胞の仕組みを利用して増殖しなければなりません。つまり、ウイルスの感染には、手間がかかるのです。ウイルスが体に入り込み、細胞の中に取り込まれて、初めて増殖できるわけです。
さらに、ウイルスが侵入した細胞が、免疫担当細胞に発見されると、ウイルスの増殖が進む前に排除されてしまいますので、ウイルス感染の成立までのハードルはたくさんあります。ウイルスがいても体に入り込まなければ感染しませんし、入り込んでも細胞に取り付けなければ感染は成立しません。もし取り付いても、細胞の中に入り込まなければ、やはり感染しないのです。感染の成立の確率は意外と低いのです。
このことは、1人のウイルス感染者の周りに10人の未感染者がいた場合、何人にうつるかを示した「絶対再生産数」によっても明らかです。新型コロナウイルスの場合、10人中2ないし3人と推定され、手当たり次第に感染するものではなく、ある人が感染するかどうかは、確率の問題であることが分かります。
実際の感染では、感染するときの環境(会食、三密)や、マスクの使用などに左右されますので、それを加味した数値が「実効再生産数」になります。新型コロナウイルスの感染拡大第3波の北海道で、1・7程度と算出されます。1人の感染者から新たに出た感染者は2人程度という計算です。やはり確率に左右されることになります。
感染の確率が高い条件、すなわち、会食や密集、密接、密閉の三密、マスクの未着用、手洗いをしないことなどを避けるのはとても重要です。しかし、もし感染してしまったとして、それ自体は確率の問題であり、感染した人が責任を負う必要は何もなく、周りが非難をする理由は全くないのです。感染者差別こそ問題なのです。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)
(北海道建設新聞2021年4月23日付3面より)