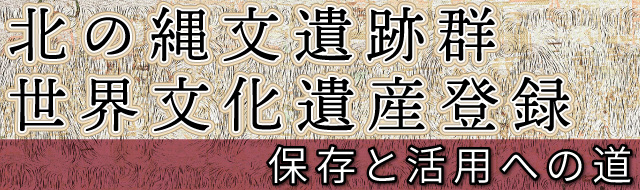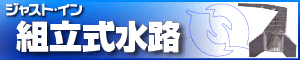ガイド育成、縄文を身近に
噴火湾に面する洞爺湖町の入江・高砂貝塚。入江は約3800年前、高砂は約3000年前の遺構。町は両貝塚の公園化とガイダンス施設の再整備を完了。周辺環境も含め、大きな整備は一区切りついたとの認識だ。
両貝塚がある場所は住居系の用途地域に指定されていて、住宅地の下に多くの遺構が存在する可能性が高く、町では「アクセス改善を目的に道路などを新設することは考えていない。既存道路の標識を充実するほか、舗装面に縄文時代をイメージする装飾を施すことを検討している」と話す。
伊達市の北黄金貝塚は約7000年から約5500年前の大規模な貝塚を伴う集落跡。市は2001年に公園化を完了。園内の地中に多くの遺構、遺物が保存されている。ガイダンス施設も備え、小学生の修学旅行などで年間1万人が訪れる。

北黄金貝塚のある伊達市では市役所庁舎に記念看板を設置。
遺跡の継承へ決意を新たにした
自然の地形を生かし人工的なものを控える形で縄文時代の暮らしを再現したことが遺産の選定段階でも高い評価を得た。
市教育委員会では「未来に継承するのが目的。世界遺産になったことに浮き足立たず、保護と活用の両輪で進める」と語る。これから保存整備に取り組む自治体の参考事例となりそうだ。
函館市の南茅部地域に位置する垣ノ島遺跡は約9000年前から、大船遺跡は約5500年前からの定住跡。どちらも住居跡と葬送などの場となった盛り土遺構から成る。市は17―20年度に垣ノ島遺跡の保存整備に取り組んだ。
整備に当たっては住居跡に立ち入れるようにしたり、実際の出土物を使った発掘体験コーナーを設けるなどより身近に縄文文化を感じられるよう工夫した。
その一方、「縄文遺跡は城や神社などと異なり、目で見て理解してもらうのが難しい」(工藤寿樹市長)という課題も認識していて、遺跡に常駐し説明役のガイドを育成するなど、対策を図る。「ガイドを通じて文化財保護の重要性も伝えていきたい」(市教委文化財課)としている。
市は今回の世界文化遺産登録を契機とした周遊観光の促進も期待。函館開建が南茅部地域で整備する国道278号尾札部道路の全線早期開通を、これまで以上に要請する考えだ。函館、鹿部、七飯、森、八雲など人口減少が進む噴火湾沿岸地域の活性化のチャンスと捉えている。
(函館支社・鳴海太輔、建設・行政部・瀬端のぞみ、室蘭支局・星野貴俊が担当しました)
(北海道建設新聞2021年8月12日付1面より)