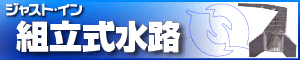北海道開発局は13日、道の駅を拠点とした中継輸送の実証実験結果を公表した。ドライバー1人当たりの運転・拘束時間を削減したことで輸送費用が低減したほか、トラックからの二酸化炭素(CO₂)排出量も並行して軽減。カーボンニュートラルの取り組みに寄与するものとなった。一方、荷物集荷のタイミングを合わせるための工夫などが今後の課題として上がっている。

24年から始まる時間外労働規制に対応するため、運送事業業者らを支える施策を展開する
実証実験は2021年11月9―12日の午前中、旭川開建とヤマト運輸が道の駅「もち米の里☆なよろ」で実施。札幌―枝幸間の単独輸送を、同駅でトレーラーヘッドを交換する中継輸送に切り替えて比較した。
単独輸送は片道約300kmの道のり。ドライバーの拘束時間(運転、休憩、荷役などに要する時間)は往復で約13.5時間に上る。
これを中継輸送とした結果、札幌―名寄―札幌のルート(A)では拘束時間が約8.5時間となり、約5時間低減。枝幸―名寄―枝幸ルート(B)では約7.5時間と、約6時間低減した。
人件費・トラック燃料費・高速道路料金などの輸送費用は、単独輸送時の約14万円に比べ、A・Bルートの合算で約45%減の約7万8000円に縮減。輸送に必要な燃料が低減され、CO₂排出量は約950kgから約50%減の約480kgにとどまった。
今後の課題・ニーズについて、運送事業者からは「実験期間中は荷物集荷のタイミングが合わず、片荷輸送のケースがあった。輸送効率をさらに高める工夫が必要」などの意見が上がった。あるドライバーは「一般車両と分離した動線、専用の駐車スペースなどがあるといい」と話している。
開発局は、同駅での実験を22年度も継続。夜間時やトレーラー以外の中継輸送の可能性などを探る方針だ。他の道の駅への水平展開を見据え、中継輸送に必要なスペースなどの課題整理を進める。