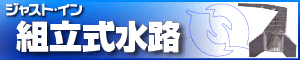予算縛られず優れた設計案 過去から引き継いだもの大切に
バルト3国の一つ、エストニアで活動する建築家の林知充氏(51)が10月下旬、札幌市立大の招きで来道した。林氏は首都タリンで設計事務所を共同主宰しながら、タリン応用科学大教授として教壇に立つ。公共・民間を問わず著名施設を数多く設計し、受賞も多数。これまでの歩みや現地事情を聞いた。

林知充氏
―エストニアは人口130万人強と小規模だが、街はどんな様子か。
私が住むタリンは人口約40万人の港町で、中心部から車で15分も走れば森が広がる。国土に高い山がなく、ずっと平地が続く。地震がなく、そのおかげもあって中心部には伝統的な建物が多く残っている。過去から引き継いだものを大事にする考えが根強く、性能面など何らかの理由で歴史的建築物を建て替えることになっても、その空間の象徴となる部分は、以前と違う目的で使うなどして残そうとする。そうした発想で設計コンペが催され、私の事務所も仕事を獲得している。
―人々の気質は。
真面目で引っ込み思案。日本人との共通性を話題にすることもある。国としてはスウェーデン、ロシア帝国、ナチスドイツやソ連など他国に支配されてきた歴史がある半面、どこかを支配したことはない。強い自己主張をしない裏には、支配されながらもここまで生き延びてきた民族のしたたかさがあって、ここは日本と違う部分だろう。
―どんな経緯で移住したのか。
20代で留学したバージニア工科大大学院に、エストニア出身の学生が2人いたのがきっかけだ。2人は帰国後30歳そこそこで大きな仕事を取っていて、この1人に来てほしいと誘われた。私はニューヨークの設計事務所に務めて2年目だったが、ボスに「エストニアの友人を手伝いたい」と話すと背中を押してくれた。
―学生時代から海外志向だったのか。
特にそうではなかった。バージニア工科大との縁は、横浜国立大の学部生だったとき友達に誘われてサマースクールに参加したことから始まっている。「終わったらアメリカ横断旅行をして帰国しよう」という言葉に引かれて渡航した。
スクールには刺激を受けた。普段大学では都市的、思想的な文脈から提案の有効性を論じることが多かったが、そこでは、建物内部で人がいかに快適に過ごせるかといった空間の作り方の重要性を再発見した。
―結果、アメリカに戻ることになる。
アメリカ横断を楽しんで帰国すると就職活動も大学院入試も時期を過ぎていて、進路が決まらないまま卒業した。模型作りなどのアルバイトをしながら過ごしていたが、サマースクールの記憶などから再びバージニア工科大で学びたいと考え、勉強して受験したところ幸い合格できた。
―建築家として日本とエストニアの違いをどう感じるか。
エストニアでは設計図と施工図を分ける発想がなく、建築家が現場に行って指示をする。ゼネコンのような存在はなく、施工レベルは日本に及ばないかもしれない。
一方、日本のプロジェクトはプロポーザル式が主流で、予算に縛られすぎると聞く。エストニアの設計コンペでは、優れた案をたくさん集めるために事業費を抜きにして案を募る。費用を検討するのは発注側の役目で、プロジェクト内のさまざまな調整作業で実現可能な水準に近づけていく。コスト管理も大事だが、気にしすぎるとアイデアを出しにくくなると感じる。日本ももっと自由なコンペを通じて案を求めたらいいのではと思う。
(聞き手・吉村慎司)