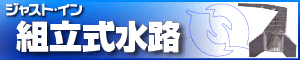新十津川も原則木造化
道内自治体で地域木材利用の機運が高まっている。道と幌加内町に次いで、新たに新十津川町が地域材利用推進方針を改正し、整備する公共建築物を原則全て木造化する。道が公表した地域材利用推進方針に準拠した。「原則全て」ではないものの、13市町が「積極的に」「可能な限り」木造化を図るよう改正している。非住宅物件での道産材利用拡大が期待される。しかし生産体制への不安をはじめ解決すべき課題は多く、道や市町村の実行力が問われる。(建設・行政部 小山龍、空知支社 室谷奈央記者)

大規模木造建築物でSGEC認証を国内初取得した
美深町立仁宇布小中学校(美深町提供)
4日付で改正した新十津川町の熊田義信町長は「団地の建て替えを計画しているところにウッドショックによる資材高騰が重なった。町有林には良質な木材があることから、今回計画を改正した」と背景を説明する。公住さくら団地の再編に町産材を活用する方針だ。
道は、率先して2022年3月に北海道地域材利用推進方針を改正。その中で「道が整備する公共施設で技術、コスト面で困難であるものを除き原則すべて木造化」と明記し、公共建築で最大限道産材活用を推進する。幌加内町、新十津川町もこの記述に準じている。
戦後、道内で進められた植樹によって成長した人工林の多くが伐期を迎えている。近年は二酸化炭素(CO₂)の吸収源として森林が重要視されるが、道内人工林のように高齢になった樹木はCO₂吸収効率が落ちる。
輸入材が高騰する中、高まる国内材の需要を踏まえ、道や市町村は高齢木を適切に伐採して使い、新しい苗木を植えるサイクルを根付かせようと努力している。
一方、同方針を改定している他の13市町では、公共施設の木造化について「積極的に推進」「可能な限り推進」などと姿勢がまちまちだ。
道水産林務部の担当者は「道と市町村では木造への対応力に差がある」と、足並みをそろえきれない要因を話す。乾燥、加工施設の有無や林道の整備具合など、製材の状況が市町村によって異なるためだ。
道は建築材の生産体制を強化するため、6月の定例道議会で梱包(こんぽう)材などの加工ラインを建築材生産に転用する場合、1m³につき3000円の支援を決めた。国に対しては、老朽化した木材乾燥機のシステム更新費用を補助する制度創設を求めている。
20年度から道と全市町村に交付されている森林環境譲与税の積極的な活用も重要だ。21年度実績では道内市町村への総交付額約26億円のうち、約15億円が森林整備や担い手確保などに充てられた。ハード投資に活用している市町村がある一方、約11億円は基金積立となっていることから、一層の積極的な活用に向けて道はセミナーなどを実施している。
これまでの取り組み成果として、適正管理された森林材を使ったことを証明するSGEC認証を取得した美深町立仁宇布小中学校や道立北の森づくり専門学院など道産材を使った建築物が近年完成している。
新十津川町は「木造化が困難なものについては、内装などの木質化を推進する」としているほか、椅子や机、消耗品にも地域材を使った木造のものを積極的に取り入れるとしている。公共施設で木材需要が高まれば伐木体制の整備推進につながり、より多くの木材が生産されるようになる。道内森林の効果的な利用に向け、自治体が先陣を切り生産と消費の循環を生み出していくことが必要だ。