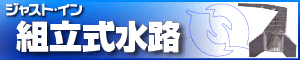役場庁舎建替など大型工事相次ぐ 学校新設も視野
留寿都村は2030年度末までに主要公共施設の再編を急ぐ。小中学校一貫化に伴う新施設建設を視野に入れるほか、公民館との統合を想定し役場庁舎を建て替える計画だ。背景には、国が指定する過疎地域から外れ、31年度以降は過疎対策事業債(過疎債)が使えなくなるという懸念がある。ただ、大規模な工事が連続すれば村財政への負担が増加しかねず、指定除外後の社会資本整備にも配慮した難しいかじ取りを強いられそうだ。

老朽化した留寿都村役場。未耐震のため建て替えが急務になっている
■人口要件が基準未満に
過疎債は、該当の各市町村が策定した計画に基づく事業の財源として発行可能な地方債。充当率100%で、元利償還金の70%が交付税措置される。借り入れには財政力要件と人口要件を満たし過疎指定を受ける必要がある。留寿都村の財政力指数は0.25前後(17―19年度)と基準の0.51を大きく下回る。
一方で人口要件は、高齢者比率と若年者比率が基本的な指定基準を満たしていない。村内に住む民間リゾート施設従業員に比較的若年層が多いためだ。1975年から40年間の人口減少率も15.1%と、基準値の28%を下回る。60年から55年間の減少率が49.6%のため、激変緩和措置により「全部過疎の指定を経過措置として受けている状態」(企画観光課)だ。
人口要件で緩和措置の廃止や基準年変更があったり、現行基準値が31年度以降も継続した場合、財政力指数が低いまま指定を外れる可能性が高い。
■大規模工事5年連続も
村は、過疎債の借り入れが確実な期間内に、大きな公共施設の更新を終えたい考えだ。
留寿都小・中の統合は義務教育学校の設置が焦点の一つで、23年度に基本構想・計画を策定、24年度に基本設計をする。新棟を整備する場合、25年度実施設計、26年度から2カ年で施工、28年度に老朽化した中学校施設を解体するスケジュールを描く。
老朽化が著しい役場庁舎の再整備は26年度基本構想、27年度基本計画と基本設計、28年度実施設計を経て、29年度から2カ年で施工する見通し。庁舎建て替えそのものは過疎債の対象メニューではないが、公民館との複合化を視野に入れている。
想定スケジュールに沿えば、26年度からの5カ年は解体を含む大型工事が連続することになる。役場庁舎建て替えは事業費の1割に当たる2億円を24年度からの4カ年で積み立てる想定。例年の当初予算一般会計が30億円前後の村にとって負担は大きい。
■新たな基金創設を検討
一般的には望ましい「過疎からの脱却」が、自治体の財政逼迫や社会資本整備停滞の引き金となりかねない。
横浜国立大の茂住政一郎准教授(財政社会学)は、自治体に十分な財源と裁量が保障されていないという地方財政制度の根本的な問題点を指摘。「過疎指定の有無を問わず、地方が自主的・柔軟に地域の必要を満たせる財源調達制度の構築など、総体的な再考が求められる」とする。一方、過疎指定を外れるまでの村の現実的な対応として「住民の同意を得つつ、必要な事業に利用可能な財源を振り向ける取り組みが重要だ」と話す。
3月の村議会第1回定例会一般質問で、佐藤ひさ子村長は特定目的基金への積み増しや新たな基金創設の検討に言及し、「施設を更新すると判断した場合、先送りせず実施に向け取り進めたい」と覚悟を示した。指定除外前の大型施設更新と、除外になった場合の将来的な住民負担増やサービス低下の回避。両立の高いハードルをどう乗り越えるか、注目が集まる。