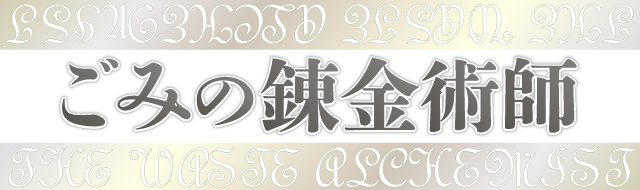照明、テレビ、車、太陽光発電と、さまざまなところで使われるガラス。製品としての役割を終えると、廃棄物として埋め立て処理や砕いて建設資材に再利用される。道立総合研究機構のエネルギー・環境・地質研究所に属する稲野浩行さんは、廃棄される蛍光管ガラスを加熱して独特な模様の装飾タイルを開発したり、太陽光パネルや自動車ガラスの再利用などを研究する〝ごみの錬金術師〟だ。

化学と美術の素地を持つエネ環地研の稲野さん
1962年札幌生まれ。幼少期は自然の中で虫取りをするのが好きで、学研の雑誌「科学と学習」などを愛読していた。中学から高校2年までの間は絵を描くことが好きで、家に帰るとポスターや版画を毎日制作。憧れは前衛的な作品で有名な横尾忠則だった。
高校卒業後は美術系の学校に進みたいと考えたが、当時の北海道は教育大など数が限られて狭き門だったため断念し、北大理学部化学科に進学した。横川敏雄教授のもとガラスの化学を学びながら美しいガラスに魅せられていった。
大学卒業後は経済的な事情もあって大学院には進まず、ガラスには直接関係のない仕事に就いた。当時、大学仲間の間ではインド旅行がちょっとしたブームで、稲野さんも就職後、職場の休みを使って10日間渡った。
ガイド本「地球の歩き方」を片手に、バックパッカーとして東インド最大都市のコルカタやヒンドゥー教最大聖地のバラナシを回った。そこで目にしたのは、アジア各国の街並みを絵にして旅費を稼ぐ欧米人や、牛糞を乾かして燃料にする地元の人々。「物が満足になくても工夫して生活すれば、仕事をしなくても何とかなる」と考え、帰国まもなく勤め先を辞めた。
「やっぱり、ガラスの仕事がしたい」と就職先を探していた頃、北海道立工業試験場の野幌分場を訪ねた。応対してくれたのはガラス工芸科の米原眞司さん。多摩美術大でガラスを学んだ後、インドでバックパッカーを経験したと聞き、初対面から意気投合。念願のガラスを職にした人生が始まった。
野幌分場では日々、吹きガラスを作ったりして汗を流した。時代とともに原料調合と作品製作の両方ができる人は少なくなり、化学と美術の素地を持つ稲野さんは重宝がられた。
働き始めて2年、上司から蛍光管のリサイクルを研究するよう指示を受けた。「俺はきれいなガラスを作るために来たんだ。そんな汚いガラスなどやってられるか」と一瞬よぎったが、上司に言われるまま研究することにした。ここから〝ごみの錬金術師〟としての歩みが始まる。