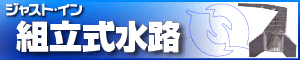工事関係者3者に聞く
基本構想の策定開始から4年、帯広大谷高改築が7月27日に着工した。この間、新型コロナウイルス感染症の発生やウクライナ情勢を背景とする資材高騰で、建築を取り巻く環境は目まぐるしく変化。設計時のオンライン打ち合わせや、工事に向けた資材の早期手配など普段と異なる対応を迫られた。今なお、先行きが見通せない中で迎えた着工の日。施主、設計者、施工者それぞれの思いを聞いた。(帯広支社・太田優駿記者)

帯広大谷高の完成イメージ
現校舎は1977年に完成。98年建設の第2体育館を除いて旧耐震基準のため、2018年に基本構想策定と設計を日建設計・創造設計舎共同体に依頼した。
工事は3月に一般競争入札で萩原建設工業が税抜き22億3150万円で落札した。管理棟、中央棟、第1体育館を改築し、教室棟(RC造、3階、延べ2842m²)を改修。新築棟はRC一部S造、3階、6715m²の規模で、敷地は校舎西側の女子サッカー部練習場を使う。
■施主「無事落札者が出るか不安だった」
学校法人帯広大谷学園(本部・音更)は、14年から計80回の検討会議を開催。19年には整備手法と事業費を決めるため、事業を一時停止したが、20年11月から基本設計に着手した。
坪坂智光事務長は資材高騰の進む中、工事が無事に落札されるか不安だった。「実施設計から工事入札まで3カ月あった。不落だと補助金などの関係から1年先送りだったので、着工を迎えられて本当に良かった」と胸をなで下ろす。
■設計者「打ち合わせはウェブ会議を活用」
設計を進める中で新型コロナウイルスの感染が拡大。行動制限などもあり、対面による打ち合わせが難しくなった。
日建設計の久保田克己執行役員は当時の対応について「本来は対面で学校の意見や要望を聞くが、事務所が札幌なので、感染者が増えると帯広まで行くのも厳しかった」と振り返る。ウェブ会議システムを打ち合わせに活用。学校側は当初、不慣れで意見がかみ合わないこともあったと話すが、実施設計の終盤にはウェブ会議のみで話し合いを進めた。
資材高騰について久保田執行役員は「急騰する直前に実施設計を終えた。影響はゼロではないが、タイミングはギリギリだった」という。来年は学園の開学100周年も控えているため、遅滞なく工事を終えられるよう願っている。
■施工者「情勢注視し臨機応変な対応を」
現場代理人を務める本保邦朗工務課長は資材について「情勢を注視して臨機応変に対応しないと、会社の赤字も増えてしまう」というが、「価格上昇は止まる気配がなく、見極めるのも難しい」と本音を漏らす。
鉄筋や鉄骨といった早期手配が可能なものはいち早く用意する考え。ただ一部の防水資材などは入手困難だという。
新築棟の完成は23年12月、現校舎改修は24年9月、解体は25年8月に完了予定。3年がかりの工事となるが「学校や設計者と密な連携が大切。事故やコロナに注意しながら安全に終えたい」と意気込む。
コロナ禍や資材高騰は、収束の兆しを見せない。建築に携わる受発注者は不安を抱えながらも、今できることは何かを意識しながら、臨機応変に仕事を進めている。