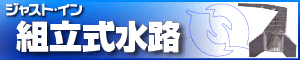時間変化を計算 実用化に向け企業連携を模索
北大の研究者らが魚介類の鮮度を簡単にシミュレーションするシステムを開発し、実用化に向けた企業連携を模索している。漁獲時間や貯蔵温度から鮮度の時間変化を計算するシステムで、小売業者、飲食店、消費者など幅広い立場での活用を想定。函館から東京へ魚を運んだ実験では計算値と実測値が高い精度で近似したという。北大発の研究が、鮮度把握という水産業界の課題解決に挑む。

スマートフォンでの使用イメージ。K値のグラフなどが示される
魚介類の鮮度はうま味に大きく影響するため、取引の重要な評価基準だ。指標としては北大の水産学者が60年以上前に提唱したとされる「K値」が業界で有力だ。
しかし、液体クロマトグラフ法など従来のK値測定法は、検査に時間がかかりリアルタイムで把握できないほか、出入荷時含む各タイミングでの分析を要する魚体の一部をサンプリングしなければならないといった課題がある。
そこで開発されたのが、数種類のパラメータを入力してK値の近似値を求めるシステム「MIRASAL」(見らさる)だ。漁獲時間や貯蔵温度、魚種などを入力すると、時間経過に応じたK値の変化がグラフで示される。うま味成分量の推移も合わせて予測できる。
さらに、漁獲場所をはじめ日時、輸送経路、配送先を指定すると、各地点でのK値をグラフやマップ上で視覚的に確かめられる。また、特定のK値の魚を特定の日時に届けたいと設定すれば、いつ漁獲すべきかを逆算できる。
アイナメを函館から東京まで運んだ輸送実験では、K値の実測値と計算値が高精度で近似したという。
システムの用途としては、漁師や市場関係者が魚をいつまでに獲って送ればいいか把握する、小売店が鮮度に応じた調理法を提案する、スーパーマーケットや回転ずし店の客が商品の鮮度を確かめるといった内容が想定される。
現在の対象魚種はブリやサバ、エビ、ホタテなど15種でさらに増やす予定だ。
鮮度計算のメカニズムには、魚体中心部からの熱移動を算出すると同時に、魚体内部の複雑な化学反応を貯蔵温度の関数として簡略に数式化するというアプローチを採用。漁船や市場など忙しい現場でのデータ入力を想定し、少ないデータ入力でのシンプルな運用を目指した形だ。
パソコンで動くシステムでスマートフォン対応も開発を進める。将来的には写真を撮るだけで漁獲時間や魚種、位置情報などが入力される仕組みを検討する。
開発したのは北大大学院工学研究院の坪内直人准教授と篠原祐治博士研究員。産業技術総合研究所(本部・東京)との共同研究で、類似プロジェクトは世界的にも存在しないという。

北大の坪内准教授(左)と篠原博士研究員
今後は興味を持つ民間企業などと意見を交換し、実用化を目指す。包装材料メーカーなどが関心を寄せているという。
坪内准教授は「漁業の高付加価値化や海外輸出の促進にも貢献できるのでは」と期待する。篠原博士研究員は「同様の計算方法を用いて肉類の鮮度計算にも取り組みたい」と意気込む。
K値が北大で考案されてから60年の時を経て、高精度で予測するシステムが同じ北大の研究者らによって開発された。「水産王国」北海道から生まれた研究が、鮮度のリアルタイム把握という業界課題をいかに改善するのか。産学連携の進展が注目される。
(北海道建設新聞2021年9月16日付3面より)