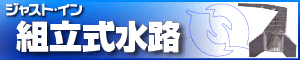実行委員長は船田慎人氏
第38回全国削ろう会北海道いわみざわ大会が、10月15、16日の2日間、岩見沢市内で開催される。道内の全国大会開催は、2003年の小樽大会以来2回目。同大会実行委員会の船田慎人実行委員長は、武部建設(本社・岩見沢)の棟梁で、大工職人の組織である大工ネットワーク北海道の代表。大会を通じ「若い大工の育成と技の継承の大切さを多くの人にアピールしたい」と意気込んでいる。(空知支社・荒井 園子記者)

実行委員長を務める
武部建設棟梁の船田慎人氏
全国削ろう会は、大工の伝統技術の継承・普及を促進する目的で、毎年場所を変えて大会を開催。大工道具のかんなで木材を削り、2日間にわたって、1000分の1mm単位の薄削りを競う。今回の大会では約200人の大工らが集結。大会長は地元の武部建設の武部豊樹社長が務める。
同時開催で、10月15日は、03年に現代の名工に選出された鵤工舎(本社・栃木)の小川三夫棟梁の対談講演会を予定。小川棟梁が、弟子の育成、大工の仕事の作法、人を育てる心構えなどについて、船田実行委員長や武部建設で働く若手大工の柳原万智子さんとの対話を通して伝授する。同16日は若手大工らを対象にした大工道具研修会を開く。
また、札幌市内で10月15、16日開催の「ほっかいどう住宅フェア2022」と連携。特設ブースを設けて、かんなの薄削りのデモンストレーションや市民向けにかんな削りの体験ワークショップを実施し、ユーチューブでライブ配信する。
船田実行委員長は大会を通じ「切磋琢磨(せっさたくま)して技能を競い、全国の大工仲間と情報交換できるのは貴重な経験」と断言。子どもや学生たちが大工の技能を間近に見ることで「将来の職業選択の一つに考えてもらえたらうれしい」と話す。
現在の家づくりは、効率化・機械化が進み、大工が担う仕事は、かつての手加工から組立作業を中心とするものに変化しているが「部材同士の接合や細かい仕上げなど、知識と技術・技能が必要なことに変わりはない」と強調。今後、AIが台頭したとしても、脱炭素社会で木造建築が増える中、「細かい手加工ができる大工の重要性が増すのでは」と予測する。
1979年6月13日生まれの43歳で、月形町出身。高校卒業後、設計に興味があったことから、札幌の専門学校に進学。デスクワークに向いていないと感じていたところ、夏休みに武部建設でアルバイトとして大工の仕事に触れ、卒業後、同社に入社した。26歳で棟梁になる。1級建築大工技能士、2級建築士。17年に設立した大工ネットワーク北海道で設立時から代表を務める。岩見沢市内で妻、高1の息子、小6の娘と暮らす。