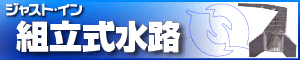系統制約や投資リスクがネック
高い潜在力を背景に計画の進む北海道の洋上風力発電。しかし系統制約、投資リスク、港湾整備など解決すべき課題も多い。2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、巨大投資によるインフラ整備、官民連携の枠組みづくり、技術開発など多様な側面からのアプローチが進められている。
洋上風力など再生可能エネルギーを道内で促進する上では、電力系統の容量確保が最大の課題だ。
道内の再エネ導入量は12年のFIT(余剰電力買取制度)開始から大規模太陽光を中心に増え続け、現在は460万㎾。道内の平均電力需要量350万㎾を優に上回る。
一方、太陽光や風力は出力変動があるため、安定供給には火力や原子力、水力など出力一定の電源稼働も不可欠だ。北海道電力ネットワークは国のルールに基づき再エネを優先して使うが、それでも再エネの出力は大きく余剰電力は日常的に生じていて、火力や水力の出力を抑えて全体のバランスを取っている状態だという。
北電ネットの担当者は「洋上風力など再エネを増やすには需要増が必須。北海道だけでは難しく本州側の需要での調整が求められる」と指摘する。
実際、余剰電力を送るための系統増強は検討が進む。北本連系線の送電容量は19年にそれまでの60万から90万㎾に増強され、さらに27年度末までに30万㎾の増強が決まっている。また、経済産業省は北海道と本州を結ぶ最大1200万㎾の新たな海底送電線敷設の検討も始まった。
再エネ発電量の変動を吸収する設備として蓄電池にも期待が掛かる。北電は17年から、系統に直接つなぐ蓄電池の設置事業者を募集。設置費用を共同負担する条件に対し、既に多くの事業者が名乗りを上げている。
投資リスクという課題も無視できない。民間事業者による地質調査や環境アセスメントといった先行投資が、事業が最終的に認められないことで無駄になる危険がある。国土交通省の担当者も「複数事業者が類似の調査をして非効率な状況」と認める。
リスク低減策として参考になるのはデンマークなどが導入する「セントラル方式」だ。政府が適地を定めて系統接続などの手続きをした上で、事業者を入札で募る。競争の公平性やコスト抑制のメリットがある。
これを踏まえて国は「日本版セントラル方式」の導入を目指す。事業初期から政府が関与して風況調査や系統確保を進める仕組みだ。実際に新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は今秋から1年間、日本海の南後志地区沖など道内外3海域で風況や地盤を調査し、結果を事業者らに情報提供する。
港湾の整備も喫緊の課題となる。既存の港湾では、岸壁の強度や風車などの資材を置くスペースが足りず、洋上風力の拠点港として国が定める「基地港湾」になれないからだ。

風力発電の建設には巨大設備の保管スペースが必要だ
道内に基地港湾はまだない。複数のプロジェクトが立ち上がっている石狩湾新港は有力候補だが、耐荷重などは今後の課題として指摘される。
室蘭や苫小牧も候補とみられている。20年に発足した室蘭洋上風力関連事業推進協議会(MOPA)の上村浩貴理事長は「室蘭港は岸壁の強度や水深が条件を満たす。洋上風力の建設・部材製造・発電の拠点化を目指す」と話す。
洋上風力発電はカーボンニュートラルへの貢献に不可欠なだけでなく、建設業や製造業、地域活性化への波及効果も期待される。道内経済を回す新しい動力源の普及に向けて、民間事業者や政府、自治体など各者の動きは本格化し始めている。
(北海道建設新聞2021年10月1日付面より)