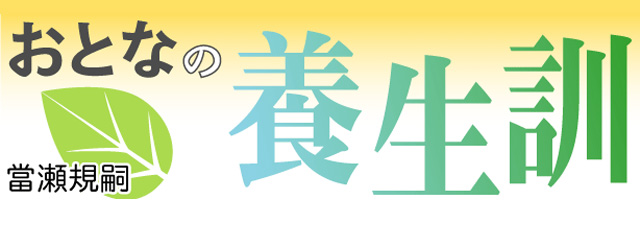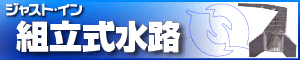ウイスキーの源になるのは、14世紀ごろにイタリアで飲まれていた、ワインを蒸留したお酒です。それはつまりブランデーなのですが、当時は、「命の水(アクア・ヴィテ)」と呼ばれていたそうです。体を温め、活力を与えると信じられて薬として飲まれていました。
でも、アルコールが体を温めるように感じるのは、アルコールが血管を広げ、心拍数を増やして、血液循環を促進するからです。体の熱はむしろ放出されるので、お酒がさめると、急に寒くなるのです。閑話休題。
アクア・ヴィテはその後、ヨーロッパ全体に広まり、スコットランドにも伝わりました。そこではブドウが取れないので、ワインではなく大麦を材料にした蒸留酒を作り始めるのですが、これをゲール語で命の水の意味の「ウシュク・ベーハー」と呼び、ウシュクの部分がなまってウイスキーというようになったのです。
なので、ウイスキーはもちろんお酒として楽しまれていましたが、薬としても使われていたのです。ウイスキーの芳醇な香りも、薬効として期待されていたのかもしれません。
今でも、イギリスではウイスキーにレモンやシナモンを入れて、砂糖を加えてお湯で割ったものを、ホットトディーと呼んで、風邪をひいたときに飲んでいます。日本のタマゴ酒みたいなものですね。
ウイスキーは、他のお酒と比べて、体に対する利点があるといわれます。一つは、蒸留を繰り返して作るので、酵母の成分が全く残りません。なので、痛風の原因となるプリン体が全く含まれていません。日本酒、ビール、ワインにはそれなりの量が含まれているのと対照的です。
さらに、樽で寝かせている間に、樽からポリフェノールが染み出てきます。ポリフェノールは、ウイスキーに色や香りを与えるのですが、最近は動脈硬化を防ぐと期待されるようになったので、ウイスキーは俄然、健康に良いお酒ということになってきました。
とはいうものの、どんどん飲んでしまえば、やっぱり体に毒です。これを防ぐには、一見逆のようですが、ストレートで飲むことをお勧めします。まず、チビリチビリとしか飲めないので、意外と量がいきません。そして、人に注がれないことです。どんどん注がれると、どれだけ飲んだかわからなくなりますからね。ただ、ストレートの時は、お水(チェイサー)をお忘れなく!
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)