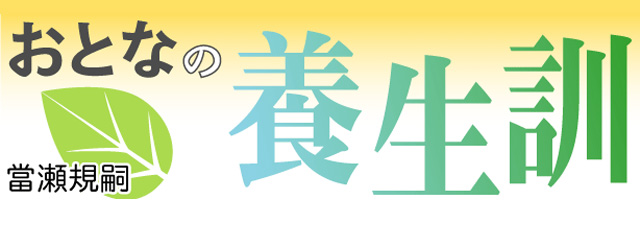上戸(じょうご)という言葉は、もともと飛鳥、奈良時代の律令制の戸籍に関わる言葉で、上戸は人数の多い家(家族)、下戸(げこ)は人数の少ない家という区分だったとか。転じて、上戸はお金持ち、下戸は貧しい家の意味になってしまったらしいのです。
これが、お酒と関連付けられて、上戸はお金持ちだから、お酒をたくさん飲む人、下戸は貧乏だから、お酒が飲めない人、の意味になりました。しかし、今はたくさんお酒を飲む人を単に上戸とは言いません。「笑い上戸」というように、お酒を飲んだ時に出てくる癖のことを指しています。
たしかに、お酒の席では、いろんな癖を持っている人に出くわします。笑い上戸、泣き上戸、怒り上戸、説教上戸、理屈っぽくなるひねり上戸、絡み上戸、機嫌がよくなる機嫌上戸…。
最近の言葉を利用してセクハラ上戸というのもあるそうですが、これはもう犯罪ですね。上戸という言葉はあてはめられていませんが、歌を歌いたがる、なにかと脱ぎたがる、電柱に登りたがる人もいましたね。
こうした○○上戸は、お酒に含まれるエチルアルコールが脳に作用して引き起こされると考えられます。日本酒の換算で早い人は2合、遅くても6合まで飲むと現れてきます。ちなみに日本酒1合のアルコールはビール中瓶1本あるいはワイン1/4本あるいはウイスキーダブル1杯に相当します。
この程度の量のアルコールは、主に脳の中の脳の活動を自制的、理性的に抑える役割を持つ神経細胞を優先的に抑制します。この結果、普段は抑え込んでいたような、感情、不満、欲求などが現れて、抑えが利かなくなるためと考えられます。でも、その結果周りの人に迷惑をかけるのでは、困ったものです。でも本人には悪気がないから始末に悪いわけです。
○○上戸に出くわしたら、どうするか。お酒を飲ませないようにするのが一番です。もう自制心はありませんから、どんどん盃を重ねてしまうので、飲酒事故につながりやすいからです。
泣いたり笑ったりワイワイ騒いでいた者が、急に静かになったら危険信号。すでに昏睡に陥っているかもしれません。急にお酒を取り上げたら、怒りだすかもしれませんから、場所を変えるといって、店を一旦出る手もあります。飲まずに外を歩けば、少しは酔いが醒めるかも。はしご酒にも効用はあるのですね。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)