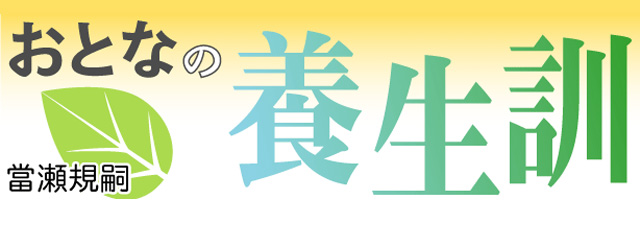酸っぱさ、つまり酸味は、食べ物に含まれている酸性物質の存在を感じ取る味覚です。酸性物質は、水に溶けると水素イオンを発生する物質で、食べ物の中には、酢酸、クエン酸、乳酸、アミノ酸など、様々な酸性物質が含まれています。
酸性は水素イオンの量で測定され、それをpH(ペーハー)で表します。pHは数字が小さいほど酸性が強いことを示します。たとえば、お酢はpH3くらいです。ちなみに、強力な酸である胃液はpH1です。実際に食べ物に酸っぱさを感じるのはpH3以下になった時だといわれます。
子供は一般に酸っぱい味が苦手です。とりわけ赤ちゃんに酸っぱいジュースなんか飲ませてしまうと、赤ちゃんは身震いして驚きます。私も子供の頃は、酢の物が苦手でした。
酸味はもともと、動物にとっては腐ったもののサインであったと思われます。腐ったものはたいていの場合、強い酸性を示すからです。腐ったものは舌に刺さる酸っぱさですよね。なので、酸味が苦手の方が、身を守れるのです。
しかし、人は人生を重ねるうちに酸味が好きになっていきます。レモンをかじったり、結構酸っぱいフレッシュジュースを飲んだり、ギョーザを酢につけて食べたり。私も、今は酢の物が大好きです。酸っぱさがおいしさに変わるのです。
酸っぱいと言えば、すし飯はもっと不思議です。酢を入れたごはんは、酸っぱさはほとんど感じませんが、酢の入らないごはんよりはるかにおいしさを感じます。実は、食べ物のpHは、食べ物のおいしさに、大きく影響するといわれています。
pH7以上、すなわちアルカリ性になってしまうと、どんな食べ物も味がぼやけてしまうといわれます。pHが4から6になると、酸っぱさではなく、他の味をおいしく感じるといわれます。
つまり、酸味は、単に酸っぱさを感じることだけではなく、弱い酸味は、むしろ前面に出なくて、他の味を引き立てて、味を引き締める役割があるのです。カツオや昆布で取っただし汁を、味付けしないで飲んでみると、うま味と塩味、そしてかすかな酸味を感じることができます。クエン酸、イノシン酸、乳酸などの味だと思われますが、このかすかな酸味がおいしさの秘密なのかもしれません。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)