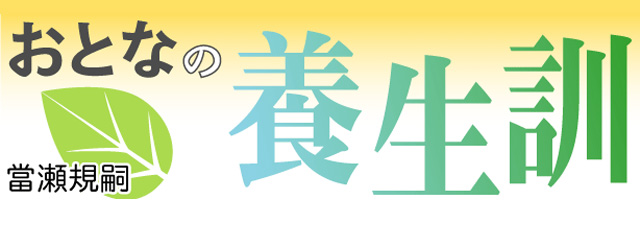飲料水の性質を示す尺度の一つとして、硬度と呼ばれるものがあります。もちろん飲料水はほとんど真水なのですが、ごく微量の成分が含まれています。その成分の中で、カルシウムとマグネシウムという金属がありますが、その含有量を示す指標を硬度といいます。含有量が多いと硬度は高くなります。硬度の高い水、すなわち硬水は、口当たりが重く、うっすらと苦味を感じます。一方、硬度が低い水、すなわち軟水は口当たりが軽く、特に日本人は飲みやすいと感じるようです。
硬水の言葉の由来には、いくつか説があるようですが、石鹸の泡立ちが悪い水というのが有力です。カルシウムやマグネシウムが石鹸の成分と結合すると、溶けにくい石鹸カスとなってしまい、泡を作りにくくなり、洗浄力も落ちます。水で洗い流しても石鹸の成分が肌に残って、なかなかスッキリしません。軟水は石鹸をすぐに泡立てることができ、水で流すと肌の石鹸がすぐに洗い流されて、すっきりさっぱりとします。
水道水が硬水か軟水かというのは、その地域の地質や水源の場所などに影響されるので、実に様々です。北海道は比較的軟水が多いとされていますが、道東など一部の地域ではかなり硬度の高い硬水が給水されています。土地土地の水道水の口当たりが変わるのは、硬度の違いが原因であるといえます。
軟水は口当たりがよく、余計な味がしないので、料理に使うのに適しているといわれます。とくに和食は繊細な味を引き出すために、軟水が欠かせないそうです。また、ご飯を炊くのも雑味がない軟水が適しているといわれます。
でも、硬水も煮込み料理などに使うと、肉などのアクを引き出す作用があり、おいしいカレーやシチューができるそうです。市販のミネラルウォーターには軟水のものと硬水のものがあるので、これを使い分けるのも一つの方法です。
製造するのに水が欠かせないお酒の場合はどうでしょうか。硬水を使うと、カルシウムが酵母の発酵を進める作用があるといわれます。なので、出来たお酒のアルコール濃度が高くなり、辛口のお酒になります。
一方、軟水では発酵が比較的ゆっくりしているので、アルコールが控えめの甘口のお酒になります。日本酒の場合、産地の水が、お酒の味わいを決定するといわれるのは、このためと考えられます。盃を傾けながら、産地の水に思いを馳せるのも悪くありませんね。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)