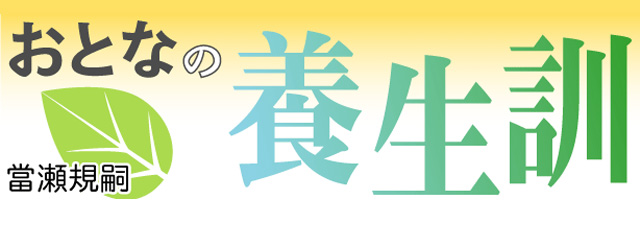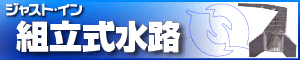もうすぐお正月です。お正月といえば、おもちを思い出す人も多いと思います。お雑煮はもちろん、きな粉もち、磯辺巻きなど、様々な料理として楽しめます。しかし、残念ながら、お正月はおもちによる窒息事故が急増する時期でもあります。毎年、各方面からおもちの事故に対する警告、警戒が発せられているにも関わらず、事故は減りません。自分だけは大丈夫と、皆さんが思っているからなのでしょう。しかし、おめでたいはずのお正月が、一転悲劇に変わってしまう訳です。用心に越したことはありません。
なぜ、おもちで窒息が起こるのでしょうか。「そりゃ、のどに詰まるからだ」と言ってしまえば、そうなんですが、おもちは他の食材にくらべて、詰まりやすい性質がそろっているのです。まず、どこに詰まるのかということです。
のど全体におもちが詰まっているということは、意外とありません。実際は、のどに引っかかるのです。引っかかる場所は喉頭蓋(こうとうがい)です。喉頭蓋は、食べ物がのどを通過するときに、気管に食べ物が入らないように蓋をするものです。おもちは粘り気があるので、閉まろうとする喉頭蓋に引っかかって、のみ込めなくなってしまうのです。のどのこのあたりはとりわけ狭くなっているので、引っかかったおもちがのどを塞いでしまうのです。
よくかまないでのみ込むから窒息すると言われますが、普通にかんでのみ込んだとしても、引っかかる恐れがあるのです。引っかからないためには、もちろんよくかんで、十分小さくすることも大事ですが、かむことで、唾液をおもちによく混ぜ込むことが重要です。唾液のネバネバ成分で小さくしたおもちを
包み込んで、のどの粘膜との間の摩擦を減らすことが肝要です。
お年寄りはのどの粘膜が乾燥しがちになっているので、おもちがのどにくっつきやすくなっているので、なおさらです。摩擦を減らすという意味では、おもちを食べるときに、汁や飲み物を合わせるのも方法です。そうすると、汁たっぷりのお雑煮は最適といえます。一方、おもちをきな粉でまぶしている場合は要注意です。
おもちで正月を祝うのですから、あわてず騒がず、心静かに、ゆっくりと味わう心掛けが肝要だと思います。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)