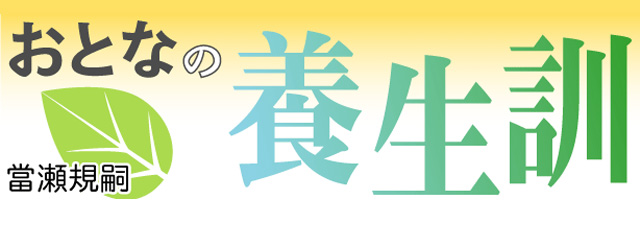激辛(げきから)という言葉はすっかり市民権を得たようで、さまざまな飲食店のメニューやスーパーの食品売り場で、激辛の文字を当たり前に見かけます。辛いものが好きな人は本当に多いようです。しかし、この激辛、あくまでもトウガラシやコショウなどのスパイスを使った料理に限られていることにお気づきでしょうか。激辛の刺身、すし、そば、なんて聞いたことがありません。ワサビや和カラシを大量に食べる人ってあまり見たことがありません。いや、無理なんじゃないかな。激辛好きの人って、意外とワサビが苦手なようです。
トウガラシやコショウは、口の中が熱くなる感じを伴っています。それで、英語では「ホット」と表現される辛さになります。この辛さは、食べ物を飲み込んでも口の中に残ります。一方、ワサビや和カラシの辛さは、つんと鼻に抜けるような感じがあり、最近は「シャープ系」と呼ばれているとか。ホット系よりは抜けが早いのが特徴です。おそらく、鼻に抜ける感覚が大量だと始末に悪いので、トウガラシ好きはワサビを敬遠するようです。
最近は日本食ブームだそうですが、それでも欧米人でワサビが平気な人はあまりいません。この二つの辛さの違いは、辛味を感じる舌の神経の装置が異なっていることによるようです。つまり、同じ辛さとはいえ、体の中で受け取るしくみは別物なのです。
激辛好きの人の中に、味覚が鈍麻している人がいるという指摘があります。人は食べ物を食べるとき、どんなに無害でも味がしないものを食べるのは苦痛なのです。そこで、どうしても味が強いものを欲しがる傾向があります。しかし、味覚が鈍麻している人は、甘さや塩味、うまみを感じにくく、その物足りなさから、辛味に頼るようになるのです。なぜなら味覚が鈍麻しても、辛味を感じる神経は鈍麻しにくいからです。
なぜ、味覚が鈍麻するかというと、濃い味付けを好み、それを続けることに一因があるようですが、加えて野菜をあまり食べないでいると、ビタミンや亜鉛が不足して、味覚鈍麻が起こるようです。野菜不足は味覚だけでなく、健康自体を害する一因であることは明らかです。周りの激辛好きの人、野菜不足かもしれません。注意してあげてください。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)