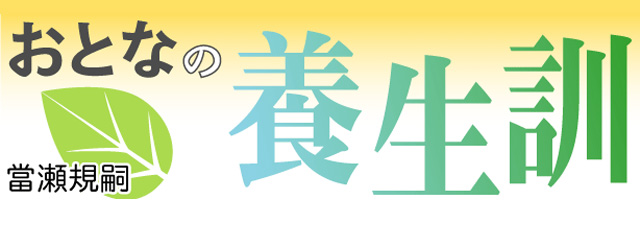朝晩の冷え込みが厳しいこの頃です。手足の冷えを強く感じて、安眠できないと悩む人が多くなります。手足や腰などに冷たさを感じ、それがつらいと思うほど強くなった状態を冷え性と呼びます。原因は体温が低下したためと、誤解されがちなのですが、実は違います。
人は、基本的に皮膚の直下に分布する神経によって、皮膚自体の温度を測り、それを脳に伝えています。例えば氷を触ると冷たく感じるのは、氷が触れた部分の皮膚を冷やし、神経がその冷たさを脳に伝えるからです。したがって、この瞬間に体温がいきなり下がるということはありません。
皮膚を温めているのは、皮下に流れ込んでくる血液です。血液は体の中心から熱を運んでくるので、皮膚を常に温めようとしているのです。特別冷たいものに触れているわけでもなく、気温が低いわけでもないのに冷えを感じるのは、皮下の血管が締まり気味になって、血流が低下しているためです。
皮下の血管が締まり気味になるのは、さまざまな理由があります。まず、気温が本当に低くなった時です。そうすると、体の熱が血流で運ばれて皮膚から失われる恐れがあるので、顔や手指や足先など外気に露出した皮膚の血管が締まり気味になり、熱の放出を防ぎます。こうして冷えを感じるのです。
これに加えて、自律神経やホルモンのバランスが乱れると、わずかな気温の低下でも血管が締まりやすくなり、冷え性を自覚するようになります。自律神経やホルモンのバランスは女性で乱れやすいと言われてきましたが、最近の研究で、男性も中年以降、男性ホルモンが低下する男性更年期となると、冷え性を自覚しやすくなることが明らかになりました。中年以降は、誰でも冷え性になる危険性があるということです。
冷え性対策で、就寝時に靴下をはいたり、手袋をはめたりする人がいますが、これは意外と逆効果です。靴下や手袋は外気を防ぎ、熱が失われないようにしますが、手足だけ暖かくなると、その熱を放出してしまおうと、手足の血管は開いてしまいます。これが繰り返されると、寒い時にも血管が開きっぱなしとなって、むしろ熱が逃げやすくなり、結局、冷え性が改善しません。
皮膚の血流を増やすには、全身の血液循環を整える効果がある運動、特に体操やジョギングなどを励行しましょう。また、血液循環の改善に効果があるショウガやニンニク、ゴボウなどを積極的に取ることがお勧めです。
(札医大医学部教授・當瀬規嗣)