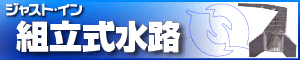堀口哲行理事長
北海道“聖地化”目指す
町おこしイベントの一つとしてアニメなどのキャラクターにふんした参加者が集って撮影などを楽しむ「コスプレ」が広まっている。新文化経済振興機構(本部・札幌)は道内でコスプレイベントを開く一般社団法人だ。コロナ禍で娯楽イベントの多くは中止や延期を余儀なくされる中、堀口哲行理事長は「新北海道スタイル」に即した新しいイベントづくりに奔走する。
―北海道開発局とコスプレイベントを開催した。
札幌駅前通地下歩行空間で2018年2月、インフラの楽しさをPRするイベント「キタフラ」を開いた。インフラとコスプレによる初の本格コラボレーションで、建設作業着をアニメ風に着こなすファッションショーは1500人を集客した。
―道内の自治体ともコラボしている。
行政との連携イベントでは苫小牧市の旗振りで始まった「とまコス」が大きい。官民の全面協力を得て企業の工場や飲食店など街を丸ごとコスプレの会場にしている。最初はおっかなびっくりだった市民も一緒に盛り上げてくれるようになり、毎年恒例行事として昨年までに7回続いている。
―コロナ禍で大規模イベントの開催が難しい状況にあるのでは。
昨年は1年で30回以上開いたが、ことしは11月まで大規模イベントは延期かオンラインに切り替える方向で調整している。〝3密〟を避ける広い会場の確保と来場者数の抑制が必要で、新たなビジネスモデル構築が急務だ。
―イベント会場の一つだった旭川市の「雪の美術館」が30日に閉館が決まった。
人気映画「アナと雪の女王」がきっかけで国内外から注目され、4回目のイベント準備をしていた矢先だった。施設存続のためにできることを模索中だ。
―運営はボランティア頼みにはならないのか。
設立当初からスタッフは全員有償にこだわってきた。食事代や移動費が持ち出しでは人も文化も根付かず、規模が大きくならない。賃金体系を整えればおのずと衣装作りなどの活動に専念できる。
―「北海道の聖地化」を目指す理由は。
愛好家の間では作品の舞台となる土地がよく「聖地」と呼ばれ、人が集まる。幸い道内が舞台のアニメやゲームは多い。コンテンツツーリズムを狙い、地域と版権元の橋渡しを担うことで、地域限定商品の開発や地元PRを促進している。
私たちは作品舞台のほか、コスプレを文化として受け入れてくれる地域も聖地だと捉えていて、どこでも対象になり得る。町ごとの悩みに合わせたイベントづくりが肝要だ。
―家で楽しめるモノ・コトが注目されるということか。
オンラインを知れば知るほど人が集まることの大切さを実感した。ライト層(初心者)は本物のコスプレーヤーとの出会いを契機に活動を本格化させる。例えば昨年、大通地区で開いた5回目の「ハロウィン大通大行進」。参加費と更衣室が無料という手軽さから3万人が集結し、一気にコスプレ人口が増えた。
―一方、イベント開催に悩む地域や施設は多い。
私たちにはオール北海道にこだわった町おこしイベント企画の経験がある。ゆくゆくは北海道のポップカルチャーを集めた物産展を開催したい。地域を元気にするために手伝えることがあれば相談してもらいたい。
(聞き手・城 和泉)
堀口 哲行(ほりぐち・てつゆき)1969年札幌出身。札幌学院大卒、タカラスタンダード入社。15年の営業職を経て、2006年に飲食・イベント運営のトライフル、12年に新文化経済振興機構を設立。複数の町おこしに関わる。
(北海道建設新聞2020年6月24日付2面より)