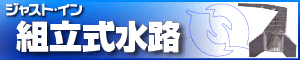平田勝二郎社長
「雪の防災」存在感高める
原野や農地を抜ける道路・線路の脇に立つ防雪柵。吹雪によるホワイトアウトを防いだり、路上での吹きだまり発生を抑えたりする、住民の生命に関わるインフラだ。ノースプラン(本社・札幌)はこうした防雪装置を企画・製造する有力業者で、メーカーでは珍しい国土交通省の建設コンサルタント登録企業でもある。平田勝二郎社長(66)に防雪装置業界の現状と自社の方向性を尋ねた。
―どんな製品を扱っているのか。
道路脇の防風・防雪柵をはじめ、斜面に付ける雪崩防止柵、トンネル入り口の上部などに付ける雪庇(せっぴ)防止フェンスなどが主力だ。板の形状や穴の開け方で風・雪の流れをコントロールする独自技術を評価してもらい、国交省や自治体、JR各社などの土木工事に納品している。道内だけでなく東北・北陸各地にも展開している。
―近年の防雪柵市場はどう推移している。
縮小が続いている。新しい道路が次々に誕生した時代と違い、新規の設置は少なくなるばかりで、仕事の7割をメンテナンス関係が占める。メンテ業務は原則的に柵材を納入したメーカーが担当するが、近年は撤退する業者も少なくない。当社は撤退・廃業したメーカーのメンテ業務を率先して引き継ぎ、結果として仕事量の確保につながっている。
―本道は年明けからの大雪で交通が混乱した。異常気象は業界にどう影響しそうか。
これからの雪害防止策について、役所があらためて検討する流れになるかもしれない。というのも、特にここ十数年の気候変動が原因で、風雪の状況が道内でも変わってきている。昔は問題なかったのに雪質の変化で危険度が上がっている場所もあれば、風が強くなったために古い施工の柵が倒れる例もある。今ある設備を補強・拡張するのか、抜本的に仕組みを見直すのか、いずれにしても気候変動に対応した方針が必要になる。
―昨夏に建設コンサルタント登録をした。業界では珍しい。
社会の中で、雪の防災に関するわれわれ専門メーカーの存在感をもっと高めたいからだ。一般的にメーカーは、物を作って売るだけの存在と見られることが多い。雪氷の知識とノウハウがあっても雪防災事業の発注関係者から「メーカーは自社製品のPRになることしか言わない」と思われている部分もあって、意見交換する機会がほとんどなかった。
とはいえコンサル事業を始めるのではない。登録することで、建設プロジェクト全体を理解できる会社だと広く認識してもらって、さまざまな関係者とつながりたい。
―コロナ禍の影響は受けているか。
公共工事向けなので大きな影響はなく、2021年12月期決算も幸い黒字を確保できた。かつては標準的な製品ばかりで他社との差別化ができていなかったが、5、6年前から独自開発に力を入れるようにした。例えば雪庇防止の部門では、降雪量が多いと普通は構造物の端から雪がせり出してくる。そこで、このせり出しを抑える形状の柵を開発したところ東北・北陸などでも好評で、受注が伸びている。
当社は私を含めて10人の小所帯だが、社会に貢献できる製品を開発して会社が成長し、社員もレベルアップする好循環が生まれつつある。今後は「雪防災のトータルシステムメーカー」としてさらに精進したい。
(聞き手・吉村 慎司)