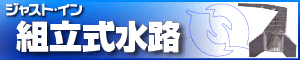増川邦弘産業立地部長
高付加価値製品を道外に
食品を中心に世界的なブランド力を持つ本道だが、企業誘致を進める上で輸送コストなどの壁も多い。全国の自治体と企業の立地マッチングなどを手掛ける一般財団法人日本立地センターの増川邦弘産業立地部長に本道が目指すべき企業誘致を聞いた。
―北海道の企業誘致の展望は。
品質の良い食品素材が豊富な北海道は、食品加工拠点として注目され続けるだろう。物流コストがネックなため、付加価値を付けた製品を道外に売るというビジネスモデルを持つ企業の誘致が求められる。
国際競争力も重要だ。外国から見れば、円安により北海道の加工食品の価値や魅力が増している。道産食材は高価格で売れるブランド力を有するため、輸出を念頭に置いた産業育成は北海道を成長させることになる。
工業製品についても輸送コストを考えれば、低単価の製品工場が道内に拠点を構えるメリットは少ない。いかに高付加価値の産業を育成・誘致ができるかがポイントとなる。
―短期的な目線ではどのような施設の誘致に期待がかかるか。
道外出荷向けの施設以外にも、道民に向けたサービスを提供する企業の誘致がある。この代表が物流施設だ。全国的にも翌日配達などECサイトに対応する物流システムが求められている。
配達時間を短縮するには分散した複数の拠点を開設する必要があるが、物流施設は商社、ファンドを中心にリゾートやホテルより確実な投資対象とみられていて、資金が集まりやすい。顧客が求める立地条件の施設を高くても買う動きがあり、国内の多くの地域でバブル的な勢いを感じる。
改築需要も根強く、「次世代型倉庫」として免震・耐震性のほか、女性や高齢者でも働きやすい荷物出し入れの容易さ、ゼロカーボンなどが求められている。
―今後北海道に求められる誘致方針は。
外から呼ぶだけが企業誘致ではない。地元企業を成長させて設備投資を促す手法もあり、地域の発展を考えるならば、そこに力を入れるべきだ。
札幌市には用地がなく、周辺自治体は一体となって確保に取り組まなければならない。札幌市は「札幌圏域」ならば他自治体での設備投資であっても補助金を交付しているが、全国的に珍しく評価されるべき取り組み。近隣自治体とのさらなる連携に期待がかかる。
地方都市への誘致は、物流コストが増大するため難しい。近隣自治体が一つの経済圏域として連携し、効率的な配送、輸出ノウハウの共有、付加価値のある産業育成などに取り組む必要がある。その中で人や物を運ぶ道路整備、優秀な人材の行き来を容易にする交通インフラ整備は大きな意味を持つ。
企業誘致では「誘致で人を増やす」という目標が地域から聞かれるが、視点を企業側に変えれば「人が居ない地域には進出できない」。若い世代の転出を減少させ、Uターンを促進する自治体の取り組みは企業誘致の大きな土台になる。
―企業誘致に関するトピックスについて。
米国の対中国政策強化により、中国に工場を立地する米国系企業と関連企業が撤退や活動縮小、今後の立地対象からの除外などの方針転換を図り、日本への立地を検討する動きが加速している。円安で日本国内での設備投資のメリットが増していることや日本への安心感も要因だ。
北海道が外資系企業の拠点として選ばれるためには、港湾・航空インフラ、広大な産業用地を提供できるメリットを増進させ、外資系企業へのフォロー体制、地域のPRを進めることが欠かせない。
(聞き手・宮崎嵩大)