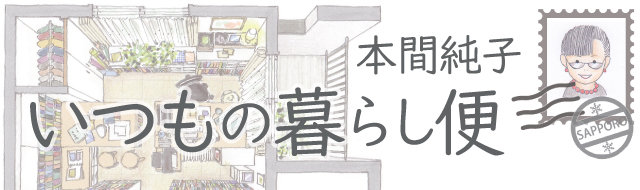今回も舞台は大通公園9丁目。スプリング遊具のアヒルとミツバチによる〝伝える色〟の仕事ぶりを紹介します。
この2匹は子どもたちとずーっと仲良しだったようで、塗り替え前はペンキがかなり薄くなっていて、ところどころに素地が見えていました。何となくアヒルとミツバチに見えるのですけれど、アヒルは目が少々怖い感じになっていましたし、もう1匹はミツバチと判明するのに少し時間がかかりました。
それぞれ鞍(くら)を背負っていて、頭の左右には、つかまるのにちょうど良いバーが付いています。鞍にまたがり握りバーにつかまって揺れを楽しむ―。そんなイメージの遊具です。比較的小さな子ども用なので、一緒に来た大人は鞍にちゃんと座って握りバーをしっかり握るよう、気を配るに違いありません。
そこで、このアヒルとミツバチの塗り替えには「青いところにちゃんと座って」「黄色いところをしっかり握って」と発信するミッションを課しました。青と黄の〝伝える色〟で、子どもたちをしっかり守ろう!という色彩計画です。

大通公園にあるミツバチの遊具
私たちは、場所を示す時、物の名前よりも色名で言ってしまいがちです。そこで、思わず出てしまうこの習慣を、そのまま色彩計画に取り入れたいと考えました。でも色名で指示すると、どの色を指しているのか分かりにくい人もいます。そのため、色そのものと色名が一致するものから選び出すことにしました。
人の色覚は生まれついてのもので、基本的に生涯変わりません。色弱の割合は小さな子どもも大人も同じです。P型やD型(色弱のタイプ)は、赤と緑は混同しやすく苦手ですが、黄と青の組み合わせは、分かりやすく得意で、色名の言い間違いもありません。この色の見え方の特性を遊具に応用することにしました。鞍は青に、握りバーは黄色に塗り、どの子どもも迷わず青い鞍に乗って、黄色のバーを握りしめることを目指します。
ただ、紫が青に、オレンジや黄緑が黄色に、近く感じる場合がありますので、紫やオレンジ、黄緑が、配色の中に含まれないことが前提です。アヒルとミツバチは、青、黄、白、黒、暗い茶色の5色で構成されています。この中で伝える色として働くものは、青と黄の2色です。全体の色数が多くなるほど伝える色が働きにくくなりますので、色選びは慎重にしたいところです。
伝える色には、信号機や道路標識のように色そのものに意味を持つものがあります。赤は禁止・停止、黄は注意・警告、青は指示に使われます。P型やD型に分かりやすいからといって、青や黄に異なる意味を持たせることは混乱の原因になります。色に新しい意味や役割を持たせる時は、多方面からの十分な検討が必要です。