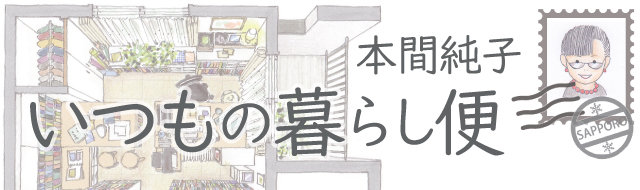中学の同期会の幹事になって、10年ほどになります。このお役目、決して率先して手を挙げたわけではありません。「ええーっ!私??」と完全に逃げ腰で、引き受ける気持ちはゼロ。なんとか逃げ切ろうと考えていたのですが、同級生の粘り強い説得に根負けしてしまいました。
コロナ禍になる少し前、同期会の打ち合わせが、幹事の一人が経営する喫茶店で開かれました。食べ物も飲み物も持ち寄りで、コーヒー代が貸切料。申し訳ないと思いつつも、ありがたい存在です。
たまたま〝おにぎりアクション〟の応募期間中だったので、持参したおにぎりの写真を専用サイトにアップしました。NPO法人のTABLE FOR TWO International(本部・東京)が企画するアフリカやアジアの子どもたちの給食を応援するプロジェクトです。アップされたおにぎりの写真に対し、協賛企業が支援協力してくれる仕組みで、今年も開催が予定されています。
さて、「いただきまーす」の後、おにぎりのラップフィルムを外しながら、フィルムに付いたご飯粒から食べ始めました。同学年のおじさんたちとおばさんたちは、全員が同じようにご飯粒をつまみながら、同じことを言います。「お米は八十八回の手がかかって作られる。粗末にしてはいけない」と。
子どもの頃に受けた教育の影響はとても強く、食べ物を大切にすることは半世紀の時を経ても身に付いて離れません。「残さず食べる」「もったいない」と言われて育ちました。
時々、フードロスが話題になります。消費者庁は「まだ食べられるのに廃棄される食品」と定義していますが、その量は年間523万t。すごく多いことは分かるのですが、具体的にイメージできません。
読み進めると「国民1人当たりお茶碗約1杯分(114g)の食べ物が毎日捨てられている」と書かれています。何か変です。おじさんもおばさんも、ラップフィルムのご飯粒を丁寧に拾い上げて食べているのに、計算上、毎日2470粒ものご飯を捨てているというのです。
捨てられるのはお米だけでなく、野菜も魚も肉も乳製品も果物も、全てが含まれます。確かに、私も冷蔵庫の奥から、すっかり忘れていた食品と再会することがあって、ちゃんと食べてあげられなかったことを深く反省します。
以前、コンビニでスイーツを買おうとしたら、わずか1時間ほどの賞味期限切れで、売ってもらえないことがありました。安心ではあるのですが、厳しいなぁとも思いました。
「商品は少量のものを買う」「残り物は翌日には食べ切る」を心掛けています。適量を作り続けるのは結構大変ですが、冷蔵庫はスカスカになり、在庫管理がしやすくなりました。まずは、うちの台所の食品ロスゼロを目指します。
食材は元々は生き物でした。食材を生産してくれた人たち、それを運んでくれた人たちの手助けがあって、私たちの身体は作られています。頂戴した命は残さず食べて、「ありがとう」を伝えたい。